現在転職活動中の方で、「ブラック企業を見分けるにはどうすれば良いか?」という悩みをお持ちの方は多いと思います。
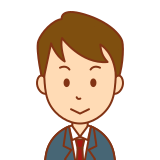
今回紹介された求人がどうも怪しい感じがするんだけどブラック企業ですかね?

「ん、なんか変だな?」と思ってちゃんと調べようという気持ちを持つのが第一歩ですよ!
採用活動を行うにあたって、企業は転職サイトや求人票には自分たちに都合の悪い事は書きません。それについては以前別記事でも書きました。
つまり表面的な情報だけでは中々ブラック企業を見分けるのが難しい場合も多いです。そしてネットなどで検索すると「〇〇に当てはまればブラック企業」といった記事が沢山出てきます。
そこで今回は元人事採用担当をしていた立場から、こうした記事の中で「個人的にも頷ける」と思えるものを6つ選び、それに対して自身の経験談や見解を交えて解説します。
まず次項で「ブラック企業の定義」に軽く触れてから本題に入ります。
ブラック企業の定義とは?

ブラック企業を画一的に定義することはそもそも難しいため、厚生労働省の関連ページからの引用を貼っておきます。
厚生労働省においては、ブラック企業について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。
引用元:労働条件に関する総合情報サイト 「確かめよう労働条件」 厚生労働省 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/zenpan/q4.html
ある人にとってはブラック企業でも、別の人にとってそうでない場合も往々にしてあります。働く価値観は感じ方は人それぞれだからです。
これを前提としたうえで、本記事では便宜上、上記の特徴を持つ企業をブラック企業として話を進めます。
先にお伝えしておきますが、以下に一つでも該当したらブラック企業とは限りません。
何らかの「怪しい」兆候を感じたとしても、それを全て避けて超ホワイト企業だけ選べる方ばかりとは限りません。他に応募の選択肢がない方も当然いると思います。安易にブラック企業と決めつけてしまう事で、応募の選択肢を狭める事にも繋がります。
仮に私が応募者ならば「以下に該当する求人を受ける場合は、(ブラック企業の)兆候又は可能性を感じるので、もう少し色々な情報を集めてきちんと自分で判断しよう」という前提で書いておりますので、ご理解のうえ読み進めて下さい。
ブラック企業を見分けるための6つの視点とは?

それではいよいよ本題です。ブラック企業かどうかを見分けるための6つの視点は以下の通りです。それぞれ1つずつ見て行きましょう。
- 職種名があいまい or わかりづらい
- みなし残業時間/裁量労働制が設定されている
- 給与額のレンジが非常に広い
- 企業トップの顔写真が出ていない
- 「夢」「やりがい」「感謝」などのワードを多用している
- 面接などで会う社員の表情が疲れ切っている
ブラック企業の見分け方1:職種名があいまい or わかりづらい
まずは「コンサルティング営業」「〇〇コンシュルジュ」など、一見カッコよく聞こえるような職種です。
例えば「コンサルティング営業」とは、一見、「戦略コンサルタント」のようなイメージを抱く可能性もありますが、実際にはコンサルではなく、新規開拓なども含む営業職と何ら変わらない場合も多いです。
純粋なコンサルタント職ならば、営業職とは別の仕事で、人脈ありきのトップセールス的なものを除けば、電話かけまくったりする営業は基本的にはやらないですよね。「具体的にどのあたりにコンサルの要素があるのか?」を事前によく確認した方が良さそうです。
また、「コンシュルジュ(=Concierge)」というのも、本来は外資由来のホテルなどで、お客様の要望を聞いて、気の利いた対応をするスタッフの事ですが、人材業界など、他の業界でも顧客の要望を聞く仕事に「コンシュルジュ」とつけて募集している場合があります。
「ライフタイムコンシュルジュ」「マンションコンシュルジュ」「転職コンシュルジュ」「婚活コンシュルジュ」など、転職サイトをちょっと検索するだけでも沢山出てきます。
本来のコンシュルジュに近そうな仕事内容も中にはあるようですが、色々読んで見ると中には「ノルマもありそうだし、ほとんど営業じゃないか?」と思えるようなものもありました。
とにかく最初に職種名を聞いてもピンと来ない事だけは確かであり、内容をじっくり読まないと誤解を招いてしまいそうです。
一般的には、あまり人が集まらない業種、職種などではこうした「一件カッコ良さそうな」ネーミングをつけて、若手の方などの応募につなげたいと考えている場合があります。
例示したものに限らず、転職サイトを見ていると、他にも横文字の”すぐに仕事内容をイメージできない職種”がたくさん出てきます。
もちろん、こうした企業/職種の全てが「ブラック」とは言いません。「ちょっとオシャレに見せたいから」ぐらいの動機なら多少は理解できますが、応募者としては職種名に惑わされず、仕事内容と実際の仕事内容に乖離がないかを事前によく確認した方が良いでしょう。
ブラック企業の見分け方2:みなし残業時間/裁量労働制が設定されている

みなし(固定)残業時間制や裁量労働制についてはご存知の方も多いかもしれません。ここではみなし(固定)残業時間を例にします。
例えば、仮にみなし残業時間が「80時間」と設定されている企業ですと、
- 「固定残業代として80時間分に相当する金額を予め基本給に上乗せで支給します」
- 「予め支給した固定残業代を超えた分は、実績に応じて支給します」
- 「残業の実績が、予め支給した固定残業代を超えない月でも減額はしません」
ざっくりですが、基本は上記ような運用になると思います。
ちなみにこの80時間という数字。労基法上の1か月の残業時間の上限は原則45時間以内であることを考えると、結構すごい数字ですよね。。
近年は働き方改革の流れで、時間外労働の上限規制や罰則の適用など、各種規制が厳しくなってきています。したがって、現在はどうか分かりませんが、以前は求人票等で「みなし残業80時間」を何度も目にしました。
参考:時間外労働の上限規制(厚労省のリーフレットへリンク)
ちなみに私自身は、固定残業代60時間と30時間の企業で働いたことがあります。あくまで私の経験上ですが、実際の残業時間は「だいたい同じぐらいか、それ以上」と考えるのが妥当と思います。
そしてこのみなし(固定)残業時間は、以下のような運用になると、途端に違法となってしまいます。
- 「固定残業代を超えた部分を追加で支給しない(深夜、法定休日の割増分もカウントしていない場合を含む)」
- 「基本給部分が低過ぎて、計算すると各都道府県の最低賃金を下回っている」
もちろん、合法的にみなし(固定)残業制度を運用している会社も沢山あります。したがって、「みなし残業あり=ブラック企業」というのではなく、
- 「みなし時間数」
- 「超過部分の支給有無」
- 「内訳の記載(「固定残業代〇円は、〇時間分のみなし残業代に相当する」と明示されているか?)」
を求人票できちんと確認するほか、「転職口コミサイト」など色々な情報から総合的に判断しましょう。ただ、あまりにも多すぎる「みなし残業時間」は注意した方が良いと思います。
ブラック企業の見分け方3:想定給与額のレンジが非常に広い

ハローワークや転職サイトの求人を見ると、想定月収・想定年収などがある程度幅を持たせて書かれています。
これ自体は問題ないですし、様々な前職給与や経験、保有スキルを持つ人を採用する事を考えれば、予算の範囲内で幅を出すのはある意味当然とも言えます。
しかし、「幅が広すぎるケース」については多少の注意が必要です。
例えば、求人票の提示年収が以下のように提示されていたとします。皆さんだったら幾らぐらいもらえそうだと考えますか?
想定年収額:350万~1,000万円
私などは事務系畑のためか、これを見たら「下限の350万が基本線で、前職給与や保有スキル、経験考慮でプラス100~150万ぐらいまでが上限かな」などと考えたりします。
実際に「完全出来高制」とかの営業職などでは、このぐらいの差が確かに出てくるのかもしれませんが、「上は多少高めに盛っておけば、人も集まりやすいだろう」と考えて、求人票にこうした誇大表記をするケースも中にはあります。
「本当に企業の核になりうる人材ならば、このぐらい出しても構わない」と考えるのも企業経営者としては本心であると思います。ただ、通常の一般的な職種で考えるとさすがに乖離がありすぎますよね。
一方、少し想定年収の幅は広いけれども、整合性が取れているパターンもあります。
想定年収:450万~800万
こちらの例では「450万円程度の主任クラスの採用をメインで想定」しているのですが、「経験次第では一つ上の課長クラスで採用しても良い」というケース。
その課長クラスの年俸レンジが800万~というような場合は何ら問題はありません。場合によっては、上限の800万円でオファーされる可能性も十分あるでしょう。
要は、色々なパターンがあるので一概に下限でオファーされるとは限りませんが、自社を良く見せるために、実際出すはずもない給与を表記しているケースも中にはあるので、きちんと確認しましょうという事です。
ブラック企業の見分け方4:企業トップの顔写真が出ていない
一般的な企業のWEBサイトには、「経営者の挨拶」が表示されているページがあります。私が企業を応募する際は必ず確認するようにしていますが、たまに顔写真を出していない場合があります。
中小零細の家族経営企業や個人事業ならば仕方ないとしても、相応の規模の株式会社でトップが顔出ししていないというのは、私個人としては「何か顔出しできない事情でもあるのかな?」と勘繰ってしまいます。やはりビジネスは信用第一ですので。
例えばですが、「BtoBビジネスや、紹介だけでやっているため、一般のお客様に対して顔を見せる必要性がない」等、事情も色々あると思いますし、企業トップの顔写真が出ていない事への受け止め方も人それぞれだとは思います。
あくまで私の場合ですが、これ以外にも複数の「ブラック企業の兆候」を感じている状態で、更に企業ホームページにも写真が出ていなければ、「大丈夫かな、信用できるかな?」と企業名や社長名でGoogle検索をしたり、転職口コミサイトで少なくともまず確認しますね。
また、メインの企業ホームページでトップの顔写真が見つからない場合でも、新卒採用サイトなどでは掲載されている場合もあるので、そちらも確認してみましょう。
ブラック企業の見分け方5:「夢」「やりがい」「感謝」などのワードを多用している

「やりがい搾取」という言葉を聞いたことがあると思います。
やりがい搾取(やりがいさくしゅ)とは、経営者が支払うべき賃金や手当の代わりに、労働者に「やりがい」を強く意識させることにより、本来支払うべき賃金(および割増賃金)の支払いを免れる行為をいう。
引用元:Wikipedia URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/やりがい搾取
転職サイトの求人でも「夢」「やりがい」「感謝」などのワードを多用しているものを割とよく見かけます。
確かに、お金のためだけにやりたくもない仕事を続ける事は辛いものがあります。働くうえで「やりがい」「夢」「感謝」なども必要な要素でしょう。
ただ、それを前面に出し過ぎる事によって、
- 「やりがいがあるんだから(=好きな事をやっているんだから)、給与面など多少は我慢できるだろう?」→(低賃金)
- 「お客様に感謝されるためには、もっとあれもこれもやらないといけないよね?」→(長時間残業)
など、「やりがい搾取をする低賃金、長時間残業のブラック企業」という構図につながってしまいます。そしてこうした過酷な環境下にあっては、上司・部下双方とも常にストレスフルな状態となり、パワハラ、過労など、更なる悪影響を引き起こしかねません。
言い換えれば、低賃金・長時間残業の実態を裏側に隠して、「夢」「やりがい」「感謝」といったワードを多用してごまかしているとも言えます。
しかしながら、これも一つの要素だけで「ブラック企業」と判断してしまうと、どんどん応募の選択肢が狭まってしまいます。「他にブラック企業の要素はないか?」「転職口コミサイトの内容はどうか?」など、複数の情報を照らし合わせて総合的に判断しましょう。
ブラック企業の見分け方6:面接などで会う社員の表情が疲れ切っている

「応募企業の人事や面接官以外の従業員の様子もできれば観察してみましょう」という話です。
以前、終業後の夜に転職の面接を受けに行った際、出迎えて頂いた社員の方の表情に生気がなく、顔色もびっくりするぐらい悪かった事がありました。内心、「うわーなんか疲れ切ってるな~。余程激務なんだろうか?」と思ったのを思い出しました。
応募企業には当然初めて行く事になるため、初めて会う方の印象はとても重要ですよね。
単純に疲れているというならば、遅くまで働いているので当然ですが、その方だけでなく、他の社員の方も何となく覇気がないというか、全体的に暗く、重苦しい雰囲気を醸しているようだと、応募する側としてはやはり「この会社大丈夫かな?」と感じてしまいますよね。
逆に、来訪者にも元気に挨拶をしてもらえたりすると、その企業への印象がグッと良くなったりもします。面接に行った時などに、廊下を歩いている社員の方を少し観察してみるだけでも色々感じ取ることができると思います。
ブラック企業の見分け方:まとめ

以上、ブラック企業の可能性を感じる場合の6つの見分け方について書いてきました。以下に纏めます。
- 職種名があいまい or わかりづらい
- みなし残業時間/裁量労働制が設定されている
- 給与額のレンジが非常に広い
- 企業トップの顔写真が出ていない
- 「夢」「やりがい」「感謝」などのワードを多用している
- 面接などで会う社員の表情が疲れ切っている
何度も書いている通り、「これらの要件に一つでも該当したらブラック企業」と決めつけてしまうことは自らの選択肢を狭める事にもつながりかねません。
逆にこれらの条件に当てはまらない場合でもブラック企業である可能性も当然ゼロではありません。
とにかく大切なのは、何度も繰り返しになりますが求人票や企業の求人原稿だけを鵜呑みにしない事、そして今回の記事も参考にして頂きつつ、複数の情報をご自身で色々と調べて総合的に判断する事です。
本記事は以上です。最後までお読み頂きありがとうございました。










