何とか無事に転職を決めたものの、入社した会社で「こんなはずじゃなかった」といった経験をされる方は非常に多いです。
筆者は、人事部の採用担当として転職者を受け入れる立場だったこともある一方で、自身も転職者として4度の転職を経験しました。
その中で双方の調査不足や説明不足など、様々な理由によってこうした転職のミスマッチが発生する事、そして振り返ってみても転職のミスマッチを100%避ける事は難しい事も実感しています。
本記事では、この転職のミスマッチにはどんなものがあるのか?そして転職のミスマッチを防ぐための考え方をお伝えします。
なぜ転職のミスマッチが起きるのか?

転職のミスマッチは本人、企業双方にとってリスクがあります。
転職のミスマッチによる退職の多くは、試用期間中又は入社1年以内に起こります。
つまり本人にとっては比較的早期の離職となり、次の就職先の面接では早期離職の理由を根掘り葉掘り聞かれる事になるでしょう。これを納得させるのは容易ではありません。
一方、企業側にとっても採用に費やした時間やコストが全て無駄になり、採用活動自体が再度やり直しになりますので、そういうリスクは少しでも避けたいと考えるのが普通です。
このように、転職のミスマッチは双方にとって避けたい事のはずなのになぜ起きてしまうのか?転職のミスマッチが発生する大きな理由としては以下の3つが挙げられます。
- 人間関係のミスマッチ
- 労働環境のミスマッチ
- 仕事内容のミスマッチ
簡単に一つずつ説明します。
1.人間関係のミスマッチ
人間関係のミスマッチは、入社後に上司や同僚とうまくなじめずに早期離職につながるケースです。
面接の段階で今後一緒に働く社員全員と会う事は不可能です。そして、人間関係では絶対的に相性が合わない人というのも残念ながら存在します。
当初一緒に働くと思っていた方が入社後すぐに異動・退職してしまい、全然相性が合わない方と一緒に働く事になったといった笑えないケースもよく耳にします。
ですので、一概に本人の対応力に問題があるとも言い切れず、結局運次第な部分も大きいです。
2.労働環境のミスマッチ
労働環境のミスマッチは、入社後に「思った以上に残業が多い」「休日が少ない」といったミスマッチです。職場内のセクハラ、パワハラなども当てはまります。
この他、各種手当や賞与など貰えると思っていたものが貰えない、労働時間の実態に見合わない給与といった待遇面のミスマッチも含みます。
こうした労働環境の全てが求人票に書いてあるわけではないですし、企業側も少なくとも私の知る限り、自社の負の部分を積極的に開示していく姿勢ではありません(=都合の悪い事は言わない)。
これに対して転職者側も応募企業について事前に十分に調べない、不明点を逆質問しないというスタンスだと、労働環境のミスマッチが発生する確率が上がってしまいます。
言い換えれば、労働環境のミスマッチは転職者側の努力次第で比較的防止しやすいとも言えます。
3.仕事内容のミスマッチ
最後は仕事内容のミスマッチです。「当初聞いていた内容と実際の仕事が違っていた」等の他、「仕事をするにあたって最低限必要なスキルが不足していた」といったスキルのミスマッチも含みます。
これも双方に原因があります。応募者側も面接に通過するために「自分を大きく見せたい」という気持ちが働き、実態よりもだいぶ背伸びした事を言ってしまい、企業側が判断を誤る場合もあります。
一方、採用する企業側でも中途採用活動を続けて行く中で、「こんな事も出来た方がいいよね」といったようにどんどん応募者への期待値が増幅し、求める人材像が変化してしまう、
そして採用現場と人事で求める人材像にいつの間にかズレが生じていたりする事も過去に経験しました。要は採用側でも十分な擦り合わせが出来ていないケースです。
とはいえ、これらはコミュニケーションの問題です。応募者側も十分に事前を準備して、企業側とのコミュニケーションの量と質を増やす事である程度対処できる分野とも言えます。
転職のミスマッチを防ぐには?
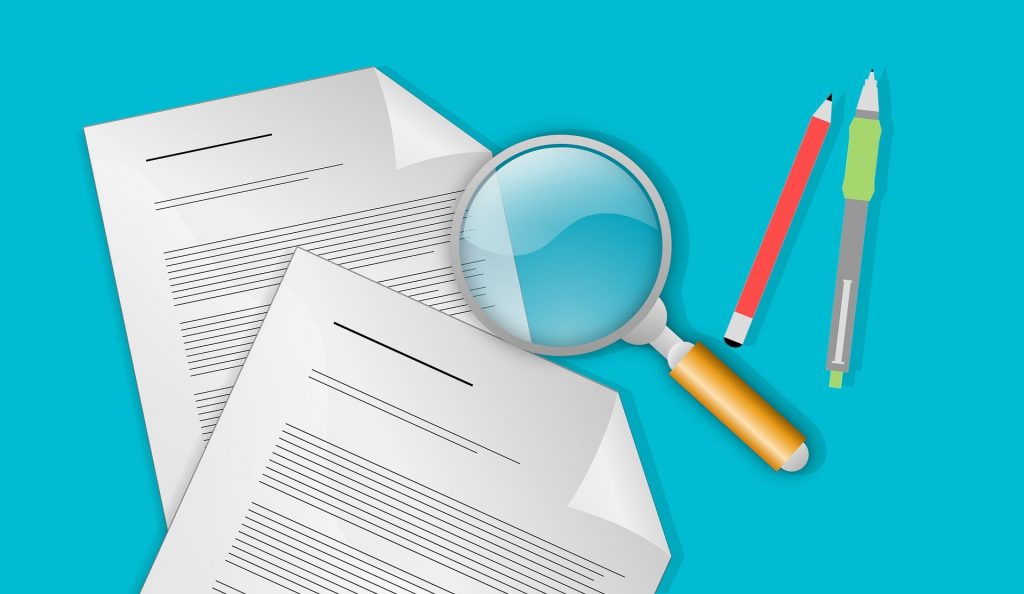
先述の転職のミスマッチが起きてしまう理由のどれもが、「自分だけではどうしようもない」要素を多少なりとも含んでおり、転職する以上こうしたリスクを完全には避けられないという事になります。
しかし、少しでもこのリスクを下げるためにはどうしたら良いのか?答えは、自己分析や企業研究をきっちり行ったうえで面接に臨むという事に尽きます(自己分析や企業研究の具体的やり方は別記事参照)。
逆に転職エージェントから紹介された求人を勧められるがままにロクに調べもせずに応募する。
そして面接では、応募企業に合格する事が目的化し、企業側にとって耳障りの良い志望動機・回答に終始する。遠慮して必要な逆質問も行わないといった転職活動をしたことはないでしょうか?(私自身も転職者として耳が痛いです)。
本来自分が描きたいキャリアがあって、現職ではそれが出来ないから転職する。転職先に対しても自分がやりたい事が出来るか否かを応募者側も厳しく見定める(少なくとも意識を持つ)。当然不明点があればきっちり質問する。これが本来あるべき姿勢のはずです。
ところが、面接官として面接をしていても「本当にウチに来る気があるのかな」「あまり深く考えていないな」とも感じ取れるような発言をしてしまう応募者は実際多いです(そうでない方ももちろん沢山います)。
こうなる原因は「自分は何故転職するのか?」「今後どうしていきたいのか?」といった自分軸が定まっていないからに他なりません。
こういう状態で仮に面接を通過したとしても、「こんなはずじゃなかった」という転職のミスマッチが起こるのはある意味必然とも言えます。
それを少しでも避けるのは、繰り返しますが自己分析と企業研究という事になります。
本記事で述べた3つの転職のミスマッチのうち、少なくても2.労働環境のミスマッチ,3.仕事内容のミスマッチについては自己分析と企業研究をきちんと行う事である程度リスクを低減できます。
本記事は以上です。転職のミスマッチを避けて、理想の転職先を見つけて頂く事を応援しています!
以下、本記事の続編記事です。
その他関連記事はこちらからどうぞ。















