以前「退職を言い出すのが怖い」というテーマで記事を書きました。
前回の記事は、自分で退職の交渉を行って円満退職を目指す場合に、どういう心構えで臨むのが良いか?、どのように上司に伝えるのが良いか?を主眼にしたものでした。
退職に関するルールなども書いておりますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。
さて、本記事は上記の続編の位置づけです(長くなるので別記事にしました)。
こちらでは自分で退職するのがどうしても難しい場合の最終手段としての退職代行の利用について、退職代行サービス業者毎の特徴や、利用する際の注意点などをざっくり纏めています。
退職代行サービスの3つの運営主体と非弁行為について

勤め先の企業へ退職の意思を伝えるというのは勇気のいる事です。
前記事でも述べましたが、労働者には退職の自由があります。しかしながら、執拗な引き留めや脅しなどで退職を撤回させようとするケースも実際には存在します。
こうした状況では、「どうしても自分から言い出せない」「円満に退職できるとは思えない」という状況も十分あり得る事です。 また、「うつ」など精神的に辛い状況の方もいるでしょう。
そうした場合の手段として「退職代行サービス」を利用するという方法があります。 退職代行サービスを行っている業者は沢山ありますが、大きく分けて3つの運営主体があり、それぞれ特長があります。
- 弁護士
- 法適合の労働組合
- 一般法人(株式会社、合同会社など)
| 運営主体 | 強み | 弱み |
| 1.弁護士 | ・確実(弁護士法72条で代理交渉権有) | ・費用が高い |
| 2.法適合労働組合 | ・労働組合法6条で労働者のための代理交渉OK、かつ弁護士より低費用 | ・役員、公務員など労働組合に加入できない方はサポート対象外 ・損害賠償請求や不当な懲戒処分など、万一訴訟に発展した場合の代理が不可。 |
| 3.一般法人 | ・手続き簡単、低費用 | ・弁護士法72条違反(非弁行為)に注意が必要。 |
検索エンジンなどで退職代行サービスを検索すると沢山情報が出てきます。まずは、上記の3つの運営主体のどれに当てはまるのかを把握したうえで、各社のサービスを比較しつつ見ていく事をオススメします。
次項では、上記に沿った具体的な留意点を幾つかお伝えしますが、ここで弁護士法72条違反(非弁行為)について触れておきます。
まず退職代行を考えるうえで、「退職の意思の伝達(=辞めたい)」と「交渉」は切り分けて考える必要があります。
弁護士以外が有償で退職にかかる退職金や残業代などの「交渉」を本人に代わって行う事は弁護士法72条(=非弁行為)違反となり違法です。
ただし、法適合の労働組合が組合員のために団体交渉を行う場合は、労働組合法6条で認められており、弁護士法72条違反にはあたりません。参考までに条文を引用しておきます。
この「非弁行為」を一旦ご念頭頂き、次項に行きたいと思います。
(参考)弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
引用元:e-Gov 法令検索より「弁護士法第七十二条」を検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(参考)労働組合法6条
(交渉権限)
引用元:e-Gov 法令検索より「労働組合法第六条」を検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
退職代行サービスを利用する際の注意点
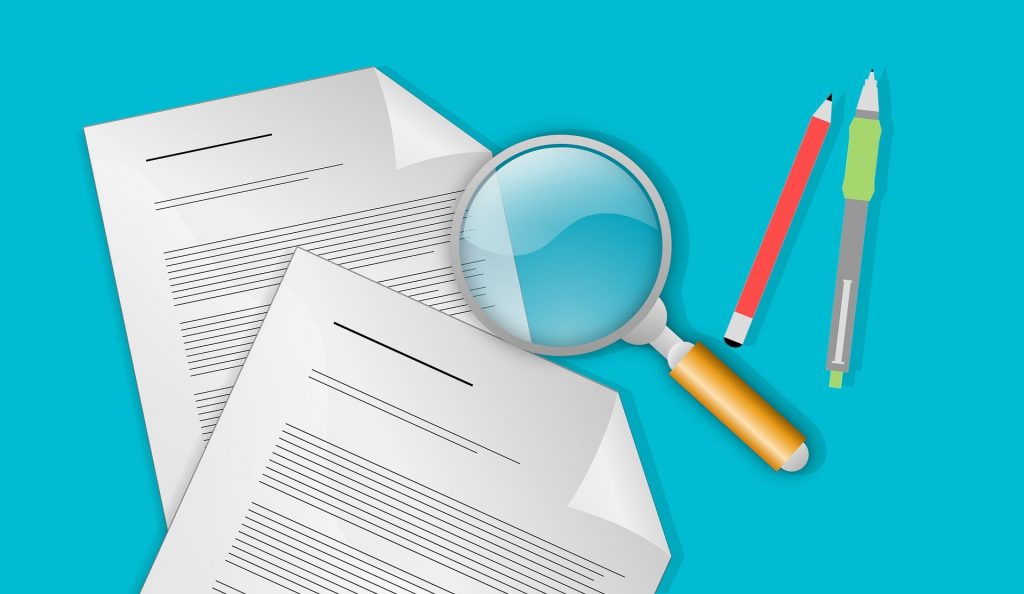
退職代行サービスの利用に際しては幾つか注意が必要です。 会社を退職するにあたっては、当然「退職したい旨の意思を伝達する」のがまず最初ですが、以下のような「交渉」が必要な場合も出てきます。
- 有休取得の交渉
- 未払い給与の対応
- 未払い残業代の請求
- 退職金の請求 など
もし仮に上記のような交渉が一切必要ない場合は、先述の表でも挙げた「3.一般法人」を利用するのが良いと思います。
一般法人は原則として「退職の意思の伝達」のみを行います。料金も他と比較して安い場合が多く、手続きも簡単です。実際にそれでスムーズに退職できるケースも多いです。
一方、先述の通り企業と交渉しなければならない場合、本人に代わって合法的に交渉を代理できるのは1.弁護士、2.法適合の労働組合が運営する退職代行サービス業者になります。
「簡単にやめさせてもらえそうにない」「会社とトラブルを抱えている」といった場合は、多少費用が高くとも1.弁護士、2.法適合労働組合のように「交渉」ができる退職代行サービスを選択するのが良いでしょう。事務手続きなどは「3.一般法人」と比べて多少あるかもしれませんが、何より確実です。
一方、退職代行サービス業者の中には以下のように紛らわしい事例(=非弁行為が疑われるケース)もあるので注意が必要です。
※労働組合といっても「使用者の経済的援助を受けない」といった幾つかの要件を満たす法適合組合である事で、労働組合法の保護の対象となり、労組法6条の代理を担う事ができます。
要件を満たさないケースとして例えば、運営会社(入金先)は使用者(元々退職代行を行っていた一般法人)で、実行は労働組合となっているようなケース。
労働組合は性質上、使用者の援助を受けることはできないことはもちろんのこと、会計は労働組合で完結する必要があります。こうした要件を満たさない労働組合(偽装労働組合)の団体交渉は非弁行為に該当する場合があります。
※一般法人が運営する退職代行サービスで「弁護士監修」となっていても、実態として弁護士は退職代行の実務に一切絡まず、無資格の事務員が企業との交渉含め全ての退職代行業務を行っている場合などは非弁行為に該当する場合があります。
利用者側としては、資格が無い法人や人が退職交渉を代行する事で企業側とトラブルになり、スムーズに退職できない、場合によってはトラブルに巻き込まれるという事態は避けたいところです。
従って、退職代行サービスの利用に際しては、先述してきたような3つの運営主体毎のメリット、デメリット、更には注意点を把握したうえで、貴方に合った退職代行サービス業者を選択しましょう。
最後に、きちんとした退職代行サービス業者を選んだ場合でも、退職代行は必ずしも成功するとは限りません。
もちろん専門の退職代行業者が対応しますので、失敗するケースは少ないと思います。
しかし、依頼者の雇用条件(有期雇用契約等)や勤怠の状況(無断欠勤が続いている等)などによっては、スムーズに退職の手続きが進まない場合もあり得る事も一応留意しておきましょう。
本記事は以上です。最後までお読み頂きありがとうございました。




