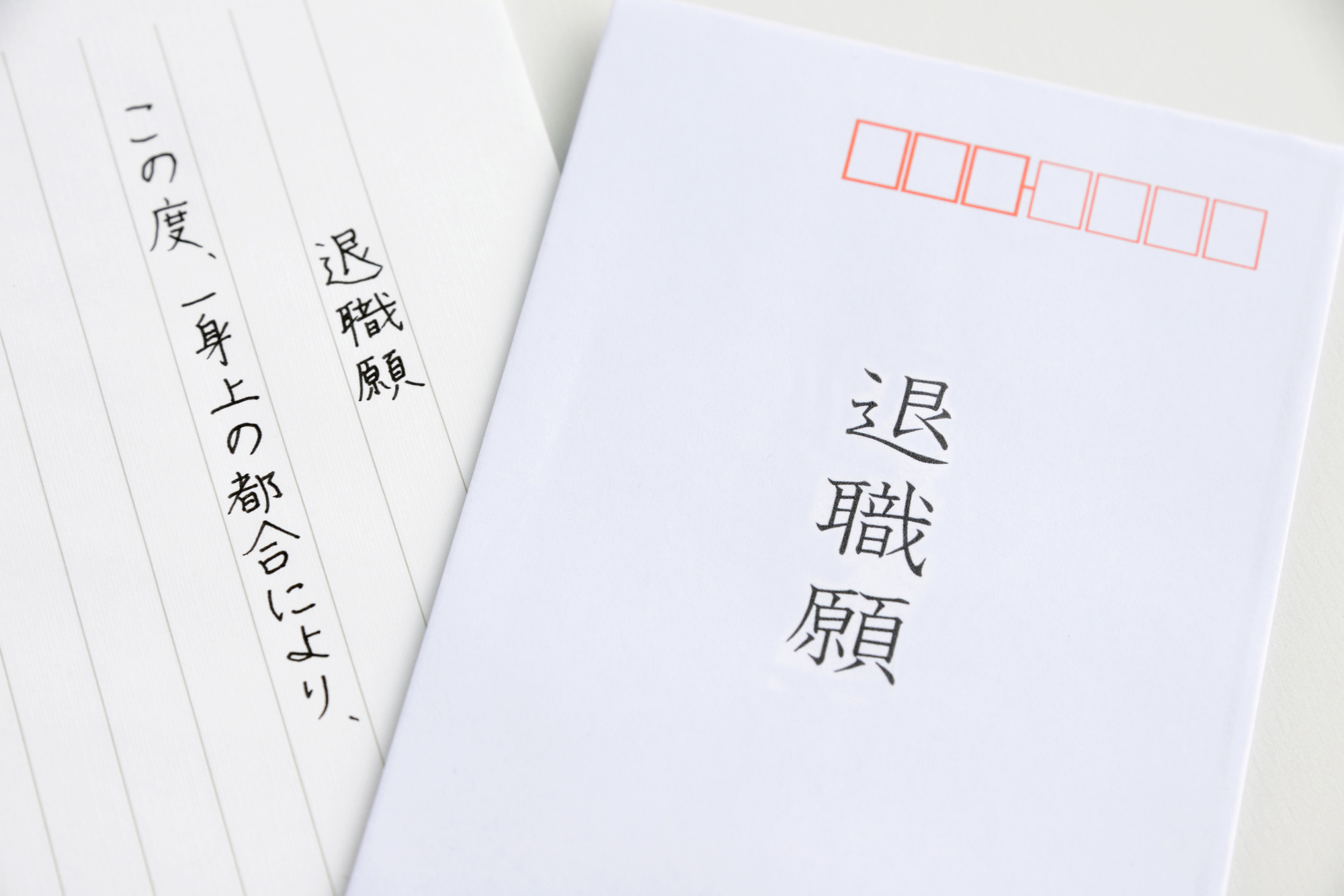退職を伝えるのが怖いのはあなただけではありません!

こんにちは。転職活動で晴れて内定が出て喜んだのも束の間、次は現職に退職する旨を伝えなければなりません。
- 上司に退職する事を伝えるのが怖い
- なんか悪い気がしてきた
とてもよくわかります。この気持ち。
今まで「こんな会社絶対辞めてやる!」と思って転職活動をしていたのに、いざ決まると何故か躊躇する気持ちが出てくるんですよね。。
私自身も以前4回転職していますが、この「退職の意向を上司に伝えること」ばかりは何度やっても慣れません。多分永遠に慣れる事はなさそうです。
つまり、「退職を伝えるのが怖い」というのは貴方だけではないという事です。そこは皆一緒です。私も「上司が仕事に追われて大変そうなので、今日はやめとこうかな・・」と思ってやり過ごした日も何度かありました。
でも必ずどこかで勇気を出して伝えないといけないですよね!
- 上司が忙しそうだから
- 周囲が忙しそうだから
この局面では、(気持ちはわかりますが)こうした忖度はもはや不要です。いずれにせよ貴方は会社を辞めて別の所へ行くのです。こうなれば少しでも早く退職の意向を伝えて、後任の決定や引継ぎなどを円滑にする方が企業のためでもあります。
私の場合、「〇月〇日までには何があっても退職の申出行う」と先に目標を決めてしまい、自分を追い込んで実行しました。自分で期限を決めるのはおススメです。
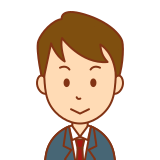
自分も期限を決めて必ず来週中に退職の意思を伝えようと思います!

その調子です!後は具体的にどう言うか?ですよね。
そこで次項以降では、現職を円満に退職する事を目指す方向けに以下についてお伝えします。
- 円満に退職するための退職理由の伝え方
- 退職に関する基本的なルールを確認
なお本記事は、ご自身で上司に退職の意思表示をして普通に円満退職を目指す事を目的とした基本的な内容です。退職代行サービスを利用する場合の留意点等については、以下の記事に纏めていますので、よろしければそちらもご覧ください。
円満に退職するための退職理由の伝え方

「お話があります、少しお時間よろしいでしょうか?」と上司に声をかけ、2人きりで対座した時の「上司もうすうす感じ取ってるんだろうな」的な微妙な空気感。
このまるで面接のような緊張感の中、いよいよ上司に退職の意向を伝えて、無事了承してもらう事になります。
ここでまず伝えるべきは「〇月〇日をもって退職させていただきたいと考えております」は当然として、その理由です。退職理由を伝える際には注意が必要です。
上司に伝える退職理由で一番避けるべきなのは、会社への不満です。例えば以下のような理由です。
- 給与が安い
- 残業が多い
- 評価が低い
- 人間関係がうまく行かない
上記が仮に事実だとしても、こうした理由を伝えられた上司は当然良い気持ちにはなりません。
「立つ鳥跡を濁さず」という格言もあるように、できれば円満に退職したいですし、こうした不満を伝えると逆に引き止めに合う場合もあります。
例えば「給与が不満なら少し改善するよ」「配置換えを検討するから」などです。上司としても以下のような思惑もあり、引き止めに動くことは十分にあり得ます。
- 今誰かに抜けられると目の前の業務がまわらなくなる。
- 新たに誰かを採用してイチから教育するのが大変。
- 自部署から退職者を出したことによる”自分自身”の評価が心配。
もしそれでグラついて会社に残ったとしても、「一旦は退職を切り出した人」というレッテルを貼られた状態では、その会社での将来はなかなかしんどいものがありますよね。
「ではどういう伝え方をすればスパッと辞められるのか?」を以下に2つほど例示します。
- 自分のキャリアを考えたときに、今後は〇〇の仕事をしたいと考えている。今の会社ではそれができないので転職する事に決めました。
上記のように自分のキャリアを軸にして「それが今の会社ではできないから転職する」というならば、余計な角も立ちません。本人がそう決意している以上、引き止めようがないですよね。
- 現在両親の介護を妻と協力してやっています。妻の負担が大きいので、今後はもう少し勤務地が自宅から近い所に就職してやっていきたいと考えております。
この家庭の事情の場合も、会社への不満ではなく個々の事情によるものですので、会社としては「それなら仕方ないね」と言わざるを得ません。
上記は一例です。基本的には転職先の面接で退職理由を伝えたときのように、「それなら退職もやむをえないな」と素直に諦めてもらえるように伝えるべきです。
さらに次が決まっている方は、以下もきちんと伝えましょう。
- 次の会社が既に決まっており、〇月〇日から入社する事が決まっております。

「やむを得ない理由だし、次も決まっている。残念だがもうウチに未練もないだろうし、これ以上引き止めても無駄だな」
個々の状況に応じて「無理のない」「やむを得ない」退職理由を伝えて、「一撃で」かつ「後腐れなく」退職する事を目指しましょう。
事務書類としての「退職届」は、上記のように「上司に口頭で退職の了承を得た」又は「退職願が受理された」等、退職日も含めて会社側と合意できたタイミングで必ず提出しましょう(後で「言った言わない」を避けるため)。※「退職願」と「退職届」は厳密には違う書類ですが、本記事では説明を割愛します。また、会社側に退職の意向が一旦承諾されると、撤回するのが難しくなる場合がありますので、会社側に退職の意向を伝える際は慎重に。
退職に関する基本的なルールを確認

次に退職する際の基本的なルールについても簡単に確認しておきましょう。
まず前提として、会社を退職するのは原則的に労働者の自由です(日本国憲法22条1項 職業選択の自由)。また、会社側は労働者の退職の意思に反して「辞めさせない」事はできません(憲法18条、労基法5条 強制労働の禁止)。
こうした前提のもと、具体的に「退職の意思をいつまでに会社に伝えなければならないのか?」について、民法627条1項で、雇用期間の定めが無いいわゆる正社員については、退職日の2週間前までに告知することが求められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
引用元:e-Gov法令検索より「民法 第六百二十七条」を検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
なお、期間の定めがある雇用契約の場合は、原則契約期間終了までは退職できません。ただし「やむを得ない理由」を除く(必要に応じて下記の民法628条、労基法附則137条(の暫定措置)も確認して下さい)。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
引用元:e-Gov法令検索より「民法 第六百二十八条」を検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
引用元:e-Gov法令検索より「労働基準法 附則 第百三十七条」を検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
一方で、各企業では個々の就業規則で「退職日の1ヵ月前」などとなっている場合が大半です。各企業がそれぞれの判断で「業務引継ぎ等に必要な期間」として規定しています。
では民法と就業規則では「どちらが優先なのか?」ですが、民法の規定が一般的には優先されますが、「円満退職」を目指す場合は、各企業の就業規則に沿って退職される方が良いでしょう。
要するに、会社の就業規則の規定を意識しつつ2ヵ月前、3か月前でも可能な限り前もって退職の意向を伝える方が、企業側も「次の準備をする余裕」ができますし、トラブルになる事も少ないと思います。
本記事は以上です。上司に退職の意向を承諾してもらえば、円満退職まであともう一歩です。業務の引継ぎも最後の義務として責任をもってやり切り、新しいステージに向かいましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。