学習初期(~年内ぐらいまで)

本記事は、社労士試験の学習方法に関する記事の(2/4回)です。前記事では、学習に先立って試験科目のグルーピングを行いました。
学習順を決めたら、後はひたすらインプット作業を続けていきます。どの科目もやり方は基本的に同じです。
- テキストの通読
- 通読した箇所の問題集を解く
他の試験学習でも同じだと思いますが、上記は両方大切です。テキストを読むだけでも、問題集を解いただけでもダメで、どちらかが欠けると定着しません。
私が1度目の受験で不合格だった際、時間短縮のため、テキストの通読を省略し、DVD講義を一通り聴いたら問題集をやる。わからない箇所だけテキストで調べるという手法を取りました。
しかし、講義は限られた時間でポイントを絞って行っているため、出題内容の全てを網羅して解説してくれるわけではありません。そのため、後から色々と知識の漏れが出てきてしまいました。
- テキストに書いてある事は最低一度は全て目を通しましょう。
なお、テキスト通読の方法ですが、私の場合「30ページ/日」と目標を決めて進めました。好みによると思いますが、私は1回目の通読ではラインマーカーはせずに、とにかくスピーディに進めました。そして、問題集を解いて分からなかった箇所を再度読み返す際、はじめてマーカーを使って行くというやり方でした。
学習の到達目安ですが、
- 直前暗記グループを除く主要7科目について、最低限テキスト通読1回&問題集1周回を年内に終わらせる。
※余裕がある方は、安全衛生法などの暗記科目も一度目を通しておいてもOKです。
このように、年内ぐらいまでで主要科目を網羅的に押さえて基礎固めを終える。そして年明けから一気に問題集を周回して実践力を養っていくというイメージです。
学習中期(年明け後~4月末ぐらいまで)
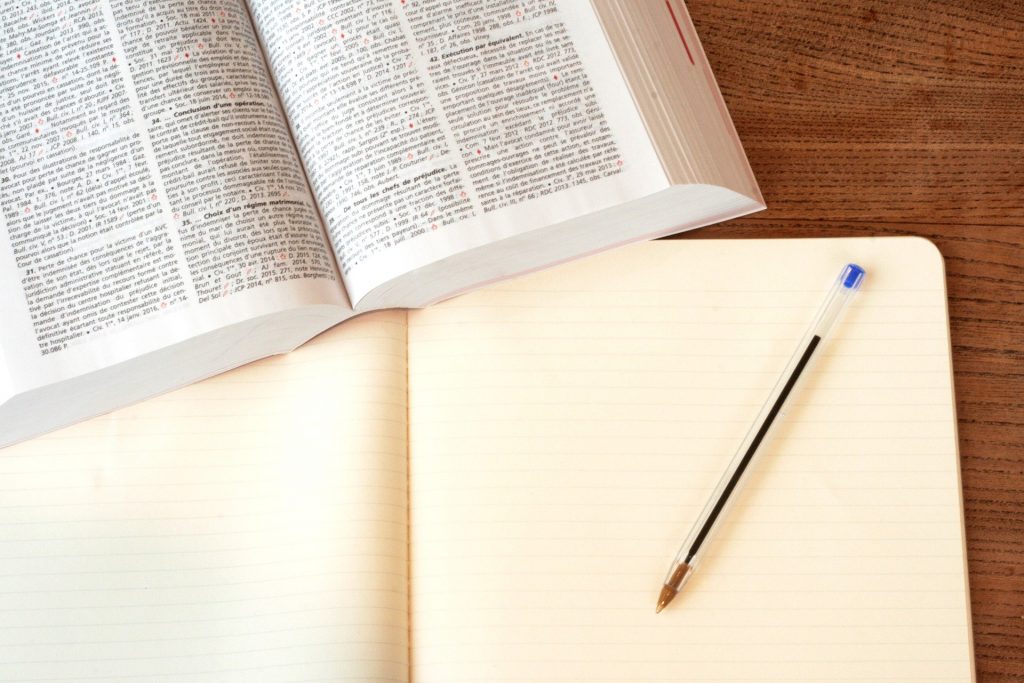
年明け以降は問題演習を中心に実践力をつけていきます。この問題演習期の基本動作は以下になります。
- 問題集を解く
- わからない箇所、理解があやふやな箇所をテキストで調べる
問題集を解いていると、試験範囲が膨大な事もあり「どんどん忘れていく」のを実感すると思います。そのため、問題集を繰り返し何度も解く事が必要です。ほかの合格者の方も、問題集を1度きりではなく何周も回しています。私の場合は本試験までに4周回しました。
そして、問題を解いて分からなかった箇所や忘れている箇所は、そのままにせずにその都度テキストに戻って確認します。
独学の場合に大変な事の一つは、テキストを読んでも理解できない箇所がたまに出てくる事だと思います。私のように通信教育ならば、付属の「質問シート」を活用したり、完全独学の方ならYou Tubeなどに誰かが動画解説をアップしている場合もあるので活用しましょう。
とにかく「わからないままにしない」ことが大切です。不明点を1個放置すると、それがどんどん増えていき、いつの間にか分からない事だらけになってしまいます。
問題演習の周回方法ですが、2周目以降は間違えた箇所だけやるという方法でも良いですが、私の場合は2周目までは正解したところも含めて全てやりました。たまたま当たっただけかもしれませんし、忘れている箇所が多いと感じたためです。
そして3周目以降は、間違えた箇所だけを重点的かつスピーディに潰していきます。3周目では、「1周目、2周目とも不正解の問題」が浮き彫りになって来ると思います。そこが自分の弱点であると認識し、再度テキストに立ち戻って理解を定着させます。
更にこの辺から、間違えた問題だけを抜き出した「オリジナル単語帳」を作成するのを是非ともおススメします。間違えた問題だけで出来上がった単語帳はまさに弱点の塊、貴方にとって最強の問題集になります。私の場合、そのオリジナル単語帳を本試験直前まで定期的に通勤電車の中などで復習しました。
そして、学習中期の到達目標ですが、
- 社労士試験の出願が始まる4月末ぐらいまでに主要7科目の問題集を最低限3~4周回終えていれば、ある程度得点力がついている事を実感できると思います。
模試で一度力試しをしてみよう

毎年試験直前期になると、大手資格予備校では模試や答練を行っています。独学の方も模試だけを単発で受験できるので、是非受験をおススメします。
私も模試だけは予備校の会場に行って受験しました。少しでも臨場感を体感しておきたかったからです(ただ、昨今のコロナの社会情勢下では会場受験を推奨するのも少しはばかられますが。。)
そしてこの段階でのスコアの目安ですが、
- 本試験3か月前の5月ぐらいの段階で、択一で6割(42/70点)程度取れていれば、残りの直前期の追い込み次第で十分合格圏内だと思います。
本試験までの残り3か月間で、これまで取り組んできた主要科目の不明箇所を引き続き潰すとともに、「安衛法」「社一」「労一」などの直前暗記科目をきちんと仕上げていけば、更に5~6点は上積みできるはずです。
逆にこの段階で択一50点を超えている人も油断は禁物です。本試験は緊張もあるのか、模試より点数が落ちるケースもあるからです(実際私がそうでした)。
いずれにせよ、この段階の模試の結果で一喜一憂するのは止めましょう。
模試の受験をお勧めした意図は、試験結果で一喜一憂するのが目的ではなく、現段階の力量を冷静に把握して、この後の直前期の学習戦略を冷静に練るためです。ここからが本当の勝負なのです。
そして模試で間違えた箇所は問題集同様に復習し、先述の「オリジナル単語帳」に追加するのも忘れずに!
本記事は以上です。次記事「合格者が語る「社労士試験」”半”独学!?勉強法 vol.3」では、大切な「試験直前期の学習内容」についてお伝えします!↓


