辞めてからの転職はやはり不利なのか?
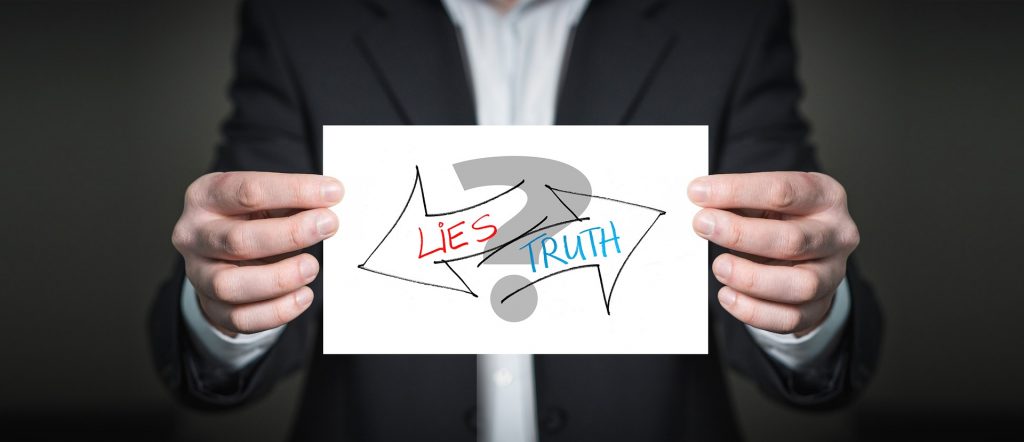
ネットなどで「会社を辞めてから転職活動するのは不利なのか?」に関する記事を見ていると、大半が「次が決まってから今の会社をやめるべき」という意見だと思いますが、皆さんはどう思いますか?
- 会社の業績不振による解雇、退職勧奨
- 病気や家族の介護などやむを得ない事情
- 度重なる長時間残業や休日出勤やパワハラなど人間関係のストレスで心身ともに消耗が激しい
こうした明らかにやむを得ない理由で退職せざるを得ない場合は別として、仕事内容や人間関係、給与、残業など、個々の様々な不満などが原因で、
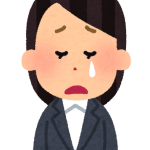
- もう限界、これ以上は持たない
- 明日にでも辞めたい
- とにかく一旦辞めてから次を探したい
という場合、「いつ辞めるべきか」を自分で決められる分だけ悩ましいところですよね。以下のような不安がよぎったこともあるのではないでしょうか?
- 「次が決まるまでに収入が途切れる期間がどのぐらいになるか?」が予測できない。
- 面接で「なぜ辞めてから転職活動をするのか?」と色々聞かれる。場合によっては足元を見られて、選考で不利になる可能性がある。
といった不安が当然出てくると思います(いわゆる”自己都合退職”だとハローワークからの失業手当も申請~受給までにおよそ3か月間の給付制限期間があります)。
以前私自身も現職中に次を決めてから退職した事もあれば、今回の記事のように一旦現職を退職してから転職活動をして苦労した経験も両方あります。また、人事部採用担当として面接する立場だったこともあります。
こうした経験からまず最初に言っておきたいのは、余程自信があるならば別ですが、「次が決まってから今の会社をやめるべき」という意見はやはり正しいと思います。
次を決めてから辞める事ができるなら、極力そうするべきだと思います。昨今のコロナ関連の「有効求人倍率の低下」、「新卒内定取り消し」や「中途採用の取りやめ、延期」などの不透明な雇用環境を鑑みれば尚更そうするべきだと思います。

「そんな事は分かっている!それでもどうしても今の会社を辞めたい。不利だろうが何だろうが、とにかくまず辞めてから転職活動をしたい。だからこの記事を見ているんだ!」
ですよね。私もそうだったので、気持ちはとてもよくわかります。転職活動に有利だからといって無理に会社に残って、心身を病んでしまったりしたら元も子もありませんしね。本人の辛さは本人にしかわからない部分もあると思います。
そこで本記事では、私自身の転職経験、人事経験も踏まえて、「不利は承知でも現職を辞めてから転職活動をする覚悟があるならば、せめてこれだけは最低限留意しておいた方が良い」という点を5つに纏めています。
- 【留意点1】確実に不利!ネガティブ要因の掛け算は挽回が困難!?
- 【留意点2】そもそもなぜ転職するのか?
- 【留意点3】失敗を最小限にするのは、辞めるまでの事前準備にあり!?
- 【留意点4】辞めてからの転職活動は意外とお金がかかる!
- 【留意点5】辞めてからの転職で怖いのは、”安易に妥協してしまう事”
※本記事は先述の通り、(やむを得ない場合を除いて)現職を辞めてからの転職活動を基本的には推奨しておりません。以下の記事内容は読者様の選考の通過や内定などを何ら保証するものではなく、記事内容を参考にされるか否かは全て自己責任でお願いします。
それでは早速一つずつ見て行きましょう。
【留意点1】確実に不利!ネガティブ要因の掛け算は挽回が困難!?


前職を辞めてから活動するという決断をされたのは何故ですか?
現職を辞めてから転職活動をしていると、当たり前ですが毎回聞かれる質問です。先述のようなやむを得ない理由でなければ、「次を決めてから辞めるのが普通なのになぜ?」と言わんばかりですよね。
そちらへの返し方は次項でご説明しますが、本項のポイントは更にその前提となる部分、つまり「辞めてから転職活動をしている」事に加えて、経歴の中に「転職回数が多い」などの更なる要素が加わってきたら?
- 転職回数が多い
- 1社の在職期間が短い
- ブランクがある
企業の面接において、上記の要因はネガティブ要因と見なされ、それぞれ納得のいく説明が求められます。明確な理由があってきちんと説明ができれば問題ないのですが、もし面接官が聞いて納得性が低ければ、「なぜ?」「どうして?」と突っ込みも厳しいですし、それだけ不採用の確率も上がっていきます。
そして、仮に上記のネガティブ要因の全部に当てはまるとした場合、「辞めてから転職活動する理由」に加え、こうしたネガティブ要因全てに対して切り返さなくてはいけません。想像してみて下さい。実際かなり大変です。
これだけネガティブ理由の掛け算になると、いかに上手に返したとしても、人事側から見た「総合的な印象」を良くするのは難しい場合も出てくると思います。少なくとも面接官が複数いた場合、全員を納得させるのはまず難しいでしょう。

一応説明の理屈は通っているけど、さすがに転職回数も多すぎるし、ブランクもある。この人採用して大丈夫かなぁ。。なんか不安。「少しでも懸念を感じたら採用しないのが採用の鉄則」という事で、(採用するのは)やめておこう。
「1社の在職期間が短い」「転職回数が多い」など、経歴上のネガティブな要因が多くなるほど、前職を辞めてからの転職活動は更に苦戦する可能性が高いので、心当たりのある方は転職の準備段階で意識しておきましょう。
【留意点2】そもそもなぜ転職するのか?
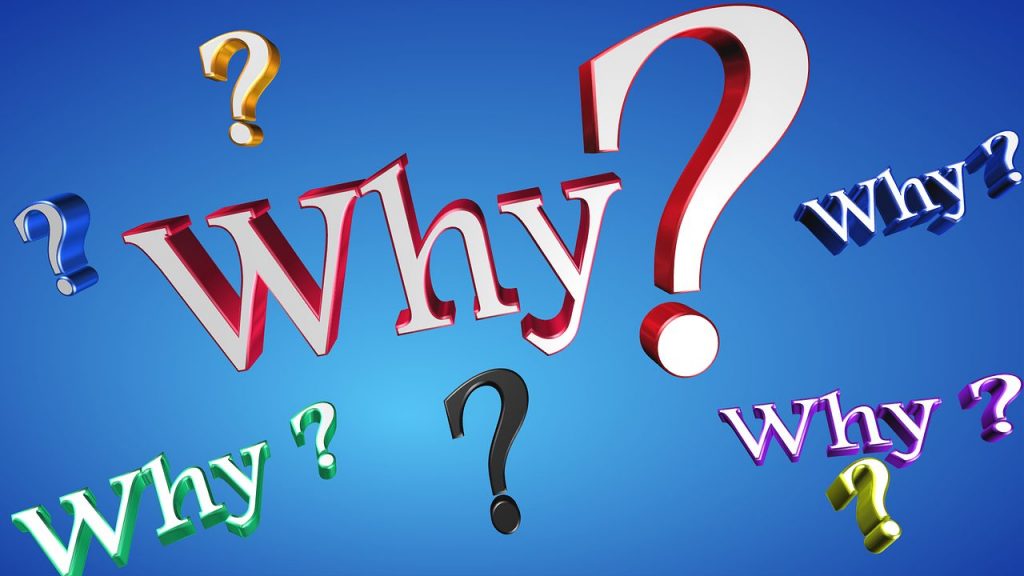
辞めてから転職するか否か。つまり「いつ辞めるか?」も大切ですが、そもそも「なぜ辞めるのか?」はそれ以上に大切です。
「残業が多い」「人間関係が辛い」といった退職理由(=不満)を面接官が納得できるレベルで説明できないと、”いつ辞めるにせよ”内定を勝ち取る事は難しいと思います。
転職(=退職)理由は、転職活動の成否を分けると言っても過言でないぐらい重要です。当ブログでは退職理由別に対策記事を書いております。退職理由については以下のリンクよりご覧ください。





そして、この退職理由さえきちんとしていれば、「なぜ辞めてから転職活動をするのか?」についてはいくらでも答えようがあります。一例ですが、自分が活動した時には以下のように伝えていました。
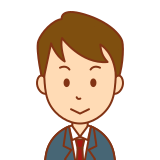
退職理由については分かりました。それでは前職を辞めてから活動するという決断をされたのは何故ですか?

「転職活動当初は現職と並行して転職活動をしていましたが、元々残業も多く、応募企業から指定された面接時間に行けない事も多く、転職活動が全く進まない事に焦りもありました。転職の意思は固く、家族とも経済面などよくよく相談したうえで一旦退職して活動に集中する事にしました」
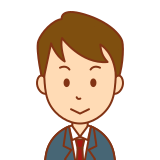
わかりました。
まずは「そもそも何故辞めるのか?」、そこから更に「なぜ辞めてから転職活動をするのか?」を一つのストーリーとして説明できるように準備しておきましょう。辞めてからの転職活動であってもきちんと相手を納得させる説明ができれば良いのです。
そして、この「納得性」については自分だけが納得できても何ら意味がありません。採用面接の場にいる大半の面接官が「まぁそれなら仕方ないか」と頷けるストーリーである必要があります(そこが難しいのですが)。できればご家族など、誰か信頼できる第三者に話してみて「客観的に納得性があるかどうか?」意見を聞いてみる事を強くおススメします。
【留意点3】失敗を最小限にするのは、辞めるまでの事前準備にあり!?

転職活動の経験がある方ならばご存知と思いますが、一般的に転職活動は就職先の決定までにある程度時間がかかります。3か月なのか半年なのか、あるいはそれ以上なのか?
まずは転職エージェントに登録して面談を受ける。そして何社か紹介してもらった中から書類選考を依頼する。通過連絡を受けたら面接日程の調整・・といった感じで、最初の面接を受けるまでに1か月近く軽くかかってしまう場合もザラです。
そして、面接を受けた後も面接結果が中々来ない事に悩まされます。ただ待つだけで月日が過ぎていく事に焦りも覚えます。
何を言いたいかというと、
現職を辞めてから転職活動をするつもりならば、辞めてから無駄な時間を浪費することなく、すぐにスタートダッシュが切れるように、以下の準備を退職前に最低限終わらせておく事をオススメします。
- 転職サイト・転職エージェントの登録
- 履歴書・職務経歴書の作成
- 前項で述べた退職理由などの面接対策
更に言うと、多少無理してでも離職前に1~2社どこかの面接を受けておくぐらいがベストです。履歴書や職務経歴書をまとめたり、転職エージェントとの面談などを通じて、
- 「どうやら転職できそうだ」
- 「少し時期尚早かもしれない」
といった感触を掴む事も可能ですし、結果として「現職でもう少し頑張ってみよう」となるかもしれません。それはそれで結果オーライです。更に、どこかの企業を応募して面接を受けたならば、面接官の反応や面接結果からも「自分の可能性」を推し量れると思います。
その結果「どうも今の状況では早期の転職先決定は難しそうだ」となっても、退職を切り出してからではもう遅いです。
すぐにでも辞めたくて仕方ない気持ちは理解できます。しかし、(大変かもしれませんが)退職前にできるだけの事前準備を終わらせる事で、辞めてから闇雲に活動するよりも「いつまでも決まらないリスク」を少しでも減らすことが出来ると思います。
また、以下は転職エージェントの利用に関しての記事です。初めて転職エージェントを利用する方は押さえておいた方が良い内容です。よろしければご覧ください。
【留意点4】辞めてからの転職活動は意外とお金がかかる!

経験のある方なら実感できるかと思いますが、現職を辞めてからの転職活動は意外とお金がかかります。
首都圏の方ならば、あちこち面接を受けに行く際に電車を使うことが多いと思いますが、これまでのように定期券は使えません。私も退職後に転職活動をして電車代が地味に痛い事を痛感しました。
この他にも、例えば面接場所に早く着いてしまったので、時間を潰すためにビル下の喫茶店に寄ったり、履歴書に貼る証明写真なども枚数がかさめば地味にお金がかかります。定期的に髪を整えたり、人によってはスーツを新調したり、といった身だしなみも印象アップのためには最低限必要ですよね。
今回主に取り上げている”自己都合退職”の場合、先述の通りハローワークの失業手当がもらえるのは退職後およそ3か月後です。収入がない以上、予想外の出費は精神が削られます。考えられるものは予め必要経費として予算化しておきましょう。
そして本項で言いたい事は、
「貰える予定の失業手当、ご自身の貯蓄を合わせた運転資金でどの程度の期間ならば無収入でも転職活動を継続できるのか?」をある程度細かく想定しておく事をオススメします。少なくとも半年程度は無収入でも耐えられるぐらいの余裕が欲しいところです。
「半年」と書きましたが、これは貯蓄額や仮にご家庭があってパートナーに収入があるか否か等でも変わってくると思いますので、本当に人それぞれだと思います。
ただし、仮に1年以上といった長期のブランクが出来てしまうと、面接そのもので不利になってしまう可能性も出てくるので注意が必要です。「3か月~半年以内には必ず決着する」という覚悟と十分な事前準備を持って臨みましょう。
【留意点5】辞めてからの転職で一番怖いのは、”安易に妥協してしまう事”

最後5つ目の留意点です。辞めてからの転職活動でもう一つ怖い事として、「転職活動が長引いて決まらない焦りから、妥協して本来の希望とは異なる会社を選択してしまう事」があります。
辞めてからの転職活動は常に不安との戦いでもあります。
- 応募したいと思える求人が全然出てこない。
- 選考結果を待つ時間が非常に長く感じる(それしか考える事がないから?)。
- せっかく最終面接まで行ったのに不合格。また”ゼロからスタート”の繰り返し。
- 貯金がどんどん減ってくる恐怖。
こうした不安を抱えながら日々を送る覚悟が必要です。そしてこの不安はブランクが長期化するほど大きくなります。転職エージェントも長期化している(=中々決まらない)人に対しては求人を紹介して来なくなります。
こうして「中々決まらない」「選択肢も限られてくる」という状況が長く続くと、「もうここでいいや、この次が決まる保証もないし」と妥協して転職活動を終わらせたくなってきます。
そして例えばですが、元々残業時間が多いのが不満で退職したつもりが、結局残業の多い会社しか選択肢がなく、そこで手を打ってしまったりという「自分でもよくわからない判断をしてしまう」事が起きたりします。しかし、これでは本末転倒ですよね。安易な妥協は更なる地獄の始まりかもしれません。
本項を一言で纏めると、「辞めてからの転職活動が長期化すると何も良い事はありません」に尽きるのですが、もし仮に長期化してしまった場合は、以下のような点を再度点検してみて下さい。
- 「決まらない理由は何か?」を再度冷静に考えてみましょう。決まらない理由としては、「面接での対応がうまくいっていない」「応募企業を高望みしすぎている」などが考えられます。
- 「仕事内容」や「勤務条件」等で絶対に譲れないもの、妥協しても良いものの整理と優先順位づけを再度行いましょう。
先ほど安易な妥協はするべきではないと書きましたが、現実的には限られた選択肢の中から選ばざるを得ない状況かもしれません。その中でも妥協できる条件と絶対に妥協できない条件があるはずです。
これらを考える上で、役立つと思われる記事のリンクを貼っておきますので、詳しくはそれぞれの記事をご覧下さい。






まとめ

現職を辞めてからの転職活動で、「失敗を最小限にするための5つの留意点」として書いてきました。
- 【留意点1】確実に不利!ネガティブ要因の掛け算は挽回が困難!?
- 【留意点2】そもそもなぜ転職するのか?
- 【留意点3】失敗を最小限にするのは、辞めるまでの事前準備にあり!?
- 【留意点4】辞めてからの転職活動は意外とお金がかかる!
- 【留意点5】辞めてからの転職で怖いのは、”安易に妥協してしまう事”
振り返ってみますと、割と現実に即したシビアな内容になったように思います。本記事を読んで「安易な離職はリスクがある」という事を知って頂きたいという思いもありました。
繰り返しますが、自分で選択できるならば、在職中に次の就職先を決めてから退職する事がやはりベストです。これは間違いありません。辞めてから転職活動に集中したとしても、希望する企業に決まる保証はどこにもありません。
しかし、それでも様々な事情で辞めてから転職活動をされる方は一定数いると思います。その際は、今回の5つの留意点を参考にしつつ、取り組んで見て下さい!

本記事は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました!
本サイトは、転職活動がうまく行かず色々悩みを抱えている方向けに”ブログ記事での情報発信”及び””個別転職相談”を行っています。以下は個別転職相談のご案内です。私自身も転職では色々と失敗もしているので、こうした経験も踏まえ、少しでも読者様のお悩み解決の役に立ちたいと思っています。
当方プロフィールはコチラ
転職相談はスキルマーケット「ココナラ」内のトークルームにて承ります。トークルームはクローズドでセキュリティが確保された環境ですので、安心してご相談頂けます。転職相談の詳細は下記をご覧下さい。
人事経験者が貴方の転職活動を戦略的にサポートします ~20代~40代可。テキストなので対面が苦手な方も安心です~※ご利用に際しては「ココナラ」の会員登録が必要になります。
ご利用者様の転職成功に向けて一緒に精一杯考えますので、是非ご利用をお待ちしております!
