※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
私自身について

平成25年、35歳の時に社労士試験合格しました。
それまで企業の人事部門で新卒、中途採用、教育研修、人事評価制度など、人事関係の仕事は10年弱経験してきましたが、社労士試験の範囲となる社会保険業務はほぼ未経験でした。
比較的小さい組織の総務であれば、何でも幅広く経験できると思いますが、規模が大きめの人事部だと担当分けしている場合も多く、私の場合「給与計算」「社会保険」などの人事労務業務は「ほぼ何も知らない状態」で試験を受験しました。それこそ「健康保険証ってどうやって取得するの??」レベルです。
社労士試験は私自身も興味はありましたが、当時の人事部の上司にも勧められたのがきっかけです。それなりに仕事も忙しく、受験を決意するまでには随分時間がかかりました。
受験を決めてから1度目は不合格、2度目の受験で合格しました。その後紆余曲折を経て、全く未経験で社労士事務所に転職して給与計算・社会保険実務を3年間経験しました。
また人事採用部門での経験があったため、業務に一通り慣れた後からは、社労士事務所内の採用面接も担当しました。採用する側、される側をたまたま両方経験したこともあり、本記事を書こうと思った次第です。
本記事は、実務未経験者で社労士試験を合格している、又はこれから学習を始めようという方向けに、実務経験を積むために就職先として社労士事務所を考えた場合に、どのような姿勢で臨むべきか?また、知っておくべき点などを纏めています。
(「社労士試験の学習方法」については本題の趣旨と異なるため、別記事で掲載しています。よろしければご覧下さい。)
社労士未経験で就職できるか?
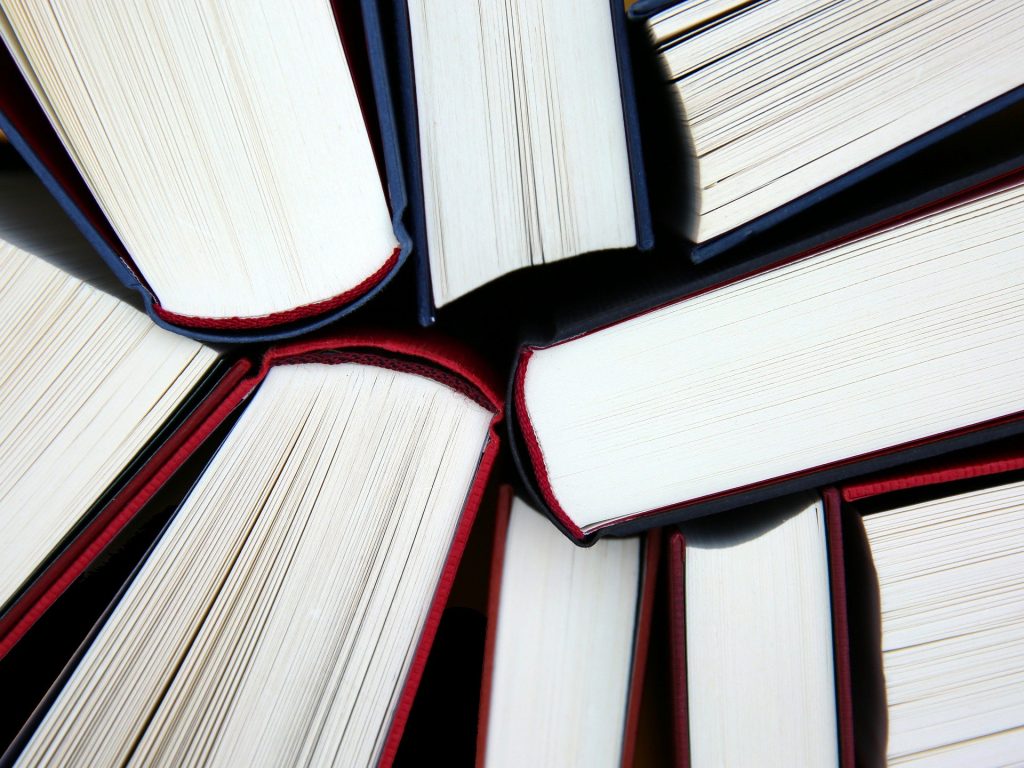
社労士試験は合格するまでに一般的に1,000時間程の学習時間が必要と言われています。
「それだけの時間と労力をかけて社労士試験をパスしても、実務未経験で社労士事務所や人事労務部門に就職できるのか?」
という疑問を持つ方は多いと思います。かくいう自分もそうでした。
これについて、あくまで1経験者としての個人的見解ですが、社労士事務所の求人が実務経験者優先なのはやはり事実ですが、条件とタイミング次第では十分チャンスはあると考えています。
以下、そう考える理由について書いて行きたいと思います。
社労士事務所の求人背景

社労士事務所は沢山ありますが、一般的に人の出入りが割に多く常に人材不足であることが多いです。
「リクナビNEXT」や「マイナビ転職」などの転職サイトや、ハローワークを見てみると、常時沢山の求人が出ているのが分かると思います。
一方、常に人材不足であるがゆえに「人は欲しい」が「教える手間を極力省きたい(すぐ辞めるか分からないし・・)」となりがちです。
社労士事務所は10人以内の少人数でやっている所が非常に多く、ギリギリの人数で業務を回しているケースが大半です。
前述の大手転職サイトの他、「ヒビコレジョブ」などの社労士専門転職サイトも存在しますが、応募資格を見てみると大半が「経験者のみ」「経験者優遇」となっています。
比較的規模の大きい事務所などでは「トレーニー枠」なるものを設けて、未経験者の募集を行っている所もありますが、実際に社労士事務所で働いてみると、「未経験者に貴重な人員を割いてじっくり時間をかけて育成する余裕は全くない状態」なのがわかります。
「実務未経験者」の評価は?

次に、社労士事務所側では社労士有資格者の実務未経験者をどう見ているのでしょうか?
これについて、一言で言えば「独り立ちまである程度時間のかかる未経験者」です。
資格と実務は別物です。社労士に限ったことではありませんが、資格があるからといってすぐに実務ができるわけではなく、逆に実務ができるからといって社労士試験に合格できるわけではありません。
例えば、社労士試験の雇用保険法の問題は解けても、「じゃあ退職者の離職票を完璧に作っておいて」と言われても実務未経験者はすぐに対応できないと思います。
社労士資格があることで「未経験者でもチャレンジできる権利を得た」ぐらいに考えておけば良いと思います。
例えば、未経験者であれば一通り仕事を覚えるのに仮に1年かかるとして、経験者ならば(経験内容と年数にもよりますが)、事務所独自のやり方や顧客のカラーに慣れるだけで3か月もあれば普通に独り立ちして、何社か担当顧客を抱えて活躍し始めているぐらいの感覚です。基本的にはどの事務所でもやることは一緒ですので。
ちなみに、「企業の人事労務部門で給与計算・社会保険業務をやっていました」という経験者の中でも色々な方がいて、「実際は外部の社労士に業務委託しており、社保書類の取次や給与計算結果のチェックしかやっていない」という場合も結構あります。
この場合は内容にもよりますが、全く何も知らない未経験者よりは良いものの、実務経験者と同等には見なされない場合が多いと思います。
実務未経験で社労士事務所に就職するには?

前述の通り、社労士事務所の求人数自体は特に首都圏に関して言えば決して少なくありません。
一方、少なくはないのですが「実務経験3年以上」など、即戦力の経験者しか応募できない求人がやはり多いです。理由は先に述べた通りですが、こうしたライバルも多い中実務未経験者が入社を決めるためにはどうすれば良いのか?
本記事では以下の4つの項目に沿って書いていきます。色々な考え方があると思うのであくまで参考の一つと捉えて下さい。
- 「実務未経験者歓迎」の求人は積極的に応募する。
- 「実務経験1年以上」等、求める経験値が低めの場合はチャンス!?
- ポテンシャル採用で前職の経験を活かす。
- 企業の人事労務部門も選択肢の一つ。
「実務未経験者歓迎」の求人は積極的に応募する

「実務未経験者歓迎」又は「実務未経験者応募可」等の求人には、経験者が応募できないわけではなく、必ずしも実務未経験者だけがライバルとは限りません。
とはいえ、こうした求人を出す事務所は少なくとも実務未経験者であっても採用する気持ちはあるはずです。実際、私が所属していた社労士事務所の所長が言っていた事があります。

よそで変なやり方が身について、それを修正できない頑固な実務経験者よりも、ポテンシャルが高い未経験者をイチから仕込んだ方が長い目で見れば良かったと思う事もあるね。
こういう考え方もあるという事です。基本的な仕事内容は一緒でも、事務所ごとに実務フローは多少違ってきます。「前の事務所ではこういうやり方だった」と固執する経験者が、新しい事務所になじめずに早期に退職していくケースを私も何度か目にしました。
このように、やる気があって素直な実務未経験者を好意的に見る事務所も少なからずありますので、諦めずに積極的に行動しましょう。
「実務経験1年以上」等、求める経験値が低めの場合はチャンス!?

社労士募集の求人を見ていると、数は少ないものの「実務経験1年以上」といった求人も目にすることがあります。
比較的数が多い「実務経験3年以上」の求人は明らかに即戦力を求めているので、未経験者では難しいと思いますが、「1年以上」というと経験者と未経験者の真ん中ぐらいの感じですよね。
あくまで私の経験上の話ですが、こういう求人は未経験者にもタイミング次第でチャンスかもしれません。
なぜかというと、募集する社労士事務所側も「採用するなら即戦力の経験者のみ!」と言っていても、人がどんどん辞めていく中で人員が確保できなければ目先の業務が回らなくなります。
こうした中ですぐに採用できなければ、次第に採用条件のハードルが下がっていく場合もありうるからです(私がいた社労士事務所では事実そうなりました。背に腹は代えられません)。
「実務経験1年以上」というのは社労士事務所側のこうした苦しい採用事情が反映された結果かもしれませんし、少なくとも「ある程度は(独り立ちを)サポートしますよ」という気持ちはあると思われます。
それならば未経験者でもタイミング次第で可能性は出てくるかもしれないので、「問い合わせしてみる」「ダメ元で応募する」など、積極的に行動していく事で道が開けてくる場合もあると思います。
もちろんその結果、「やはり経験がゼロではさすがに困る」という回答かもしれませんが。
ポテンシャル採用 ~前職の経験を活かす~

将来のポテンシャルを見越して「将来のマネージャー候補」として採用、教育する余裕がある事務所ならば、未経験の有資格者でも十分チャンスはあります。
この他、外資系企業のクライアントを持つ社労士事務所では英語が出来れば強力な武器になるため、実務未経験でも採用される確率は高くなります。
前職でこうした「マネジメント」や「英語」などの経験がある方は是非アピールしてほしいです。
小規模の個人事務所しか経験がない方から見ると、企業でのマネジメント経験は大変貴重な経験ですし、周囲を見渡しても英語を苦手としている社会保険労務士は多いです。
私自身は英語を読み書き程度ですが前職で使っていたのと、給与社保は未経験でしたが他業務での人事部経験があった事でのポテンシャル採用だったと思っています。
社労士事務所入社後に大手外資系クライアントの社会保険業務を担当した際、相手先の担当者が中国の方で日本語が苦手な方でした。そこで英語メールで比較的スムーズにコミュニケーションが出来たほか、先述のとおり事務所内の中途採用業務で面接を担当するなど、前職の経験を色々活かすことが出来ました。
この他にはやはりIT関連スキルですね。給与計算で使用する「給与奉行」などのシステムも、顧客の仕様にあった設定や必要に応じて変更が必要ですし、チェック業務や諸々の管理業務では表計算ソフト、更にはマクロやVBAなども使用して社内業務フローを構築しているケースも多いです。
そして最近は”RPA”を用いた業務改善などもブームですので、知見があれば重宝されるかもしれません。また、事務所内のネットワーク関係なども詳しい人がいればいざという時に安心です。
上記に限らず、これまでの経験の中から活かせるものないか探してみて下さい。最初はやはり「実務ありき」ですが、一通り社労士実務を経験してしまえばあとは皆横一線です。その時に、こうした「社労士+αのスキル」はきっと事務所内での貴方の強みになるでしょう。
企業の人事労務部門も選択肢の一つ

本題とは少しズレるかもしれませんが、「社労士事務所にはこだわらない。とにかく実務経験を積みたい」という場合は、企業の人事労務部門も選択肢になります。
転職エージェントを使って募集をかける社労士事務所は(予算の問題もあり)、大手でない限りはそう多くないと思いますが、企業の人事労務部門も視野に入れるならば管理部門に特化した転職エージェントに登録しておくことをおススメします。
ご参考までに「MS-Japan」社を紹介しておきます。
- 設立:1990年4月
- 拠点:東京、横浜、名古屋、大阪
- 特徴:経理・財務・人事などの管理部門及び弁護士・公認会計士、税理士などの士業に特化した転職エージェントです。※社労士の有資格者ももちろん対象です。
主に事業拠点のある首都圏にお住まいの社労士有資格者で、企業の人事労務部門に就職する事も視野に入れている方は、特にご利用をおススメします。
「リクルート」等、大手の転職エージェントと紹介案件が被る場合もあるかもしれませんが、大手が持っていない専門特化ならではの案件を紹介してもらえる可能性もあります。登録自体は無料ですので、引き出しを増やすという意味でも良いと思います。
そして先ほども書きましたが、「企業人事の給与社保担当」といっても「実務は社労士事務所等にアウトソースしており、チェックや取次しかやらない」という場合もあります。ご希望されるような実務を経験できない可能性もありますので、応募に際しては十分ご注意下さい。
未経験者の応募年齢の上限は?
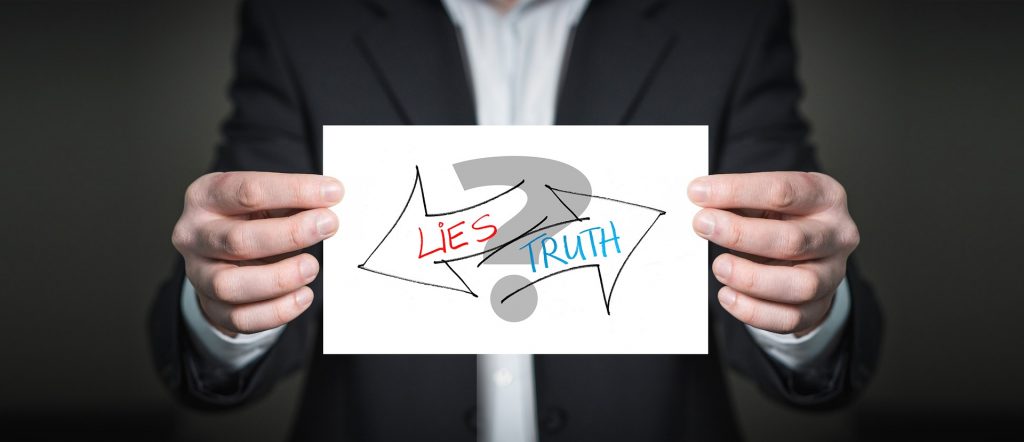
基本的には何歳でも可能性がゼロという事はありません。
ただ、主観ながら40代未経験となると実務担当者としては少し厳しくなるかなという印象です(他の職種でも同じだと思います)。
事務所内の「マネージャーや経営幹部」「システム専任担当」など異なる職種、または「届出業務のみ」「書類整理」等の純粋なアルバイト業務で入るならば話は別ですが、「未経験の正社員実務担当者」となると、事務所内で実務を教わる人が年下になることも多いと思います。こちらは気にしなくとも相手が気にしてしまう面もあるかもしれません。採用する側は組織内のバランスも考慮します。
また「社労士試験合格から5年経過」など、時間があまりにも経ちすぎている場合「ほとんど(忘れて)何も知らない状態」と見なされる可能性も高いです。
ただ、本記事でも繰り返し書いてきているように「転職は縁、タイミング」だと思っています。可能性は決してゼロではないので諦めずに行動しましょう。
所長が貴方を特に気に入れば、年齢や経験の有無などの一般論をすっ飛ばして採用が決まってしまう事もこうした個人事務所ではよく起きる事です。
終わりに

何度も繰り返し書いてきた通り、社労士事務所の求人では「即戦力の実務経験者」を求めている事が多いです。これは「実務未経験OK」の求人数と比較しても事実だと思いますし、実務未経験の有資格者が入社するのは簡単ではないと思います。
しかしながら、実務未経験者でも積極的な行動、そして運とタイミングがうまくはまれば良い事務所に就職することも可能です。
一方、実務未経験者が応募できる案件が少ない分「採用してくれるならどこでもいい!」「受かったところに行くだけ」という気持ちもとてもよく理解できますが、「行くべき事務所を見極める」という意識も持っておくべきだと思います。
社労士事務所は個人経営でやっている事務所も多いため、所長の性格次第で良くも悪くも職場環境が決まってしまうような場合もあれば、受託業務も「給与計算&社会保険」又は「社会保険のみ」「社会保険+労務コンサルティング」「助成金専門」「障害年金専門」など事務所によってかなり違います。
例えば、貴方が将来「助成金のスペシャリスト」を志しているのに、社会保険業務しか受託していない事務所に就職したら?貴方にとって必要な助成金の申請実務の経験は永遠に積めないかもしれません。
- 何のために社労士事務所に就職するのか?
- 社労士事務所に入った先のキャリアプランをどう考えているのか?
このあたりを明確にして、その目標を達成するために「自分にとって必要な社労士事務所を選ぶ」という意識は未経験者であっても持っていて欲しいと思います。
本記事は以上です。最後までお読みいただきありがとございました。

