転職活動で応募先から突如「適性検査を受けて下さい」と言われたら?
- 「適性検査なんて新卒の時から受けていない」
- 「何割取れば良いのか?」
- 「何を重視しているのか?」
など、慣れてないと疑問だらけですよね?新卒採用と違い、中途採用では適性検査自体を行わない場合もあるため、「それでも適性検査をやるという事はやはり検査結果を重視しているのか?」と心配になったりもしますよね。
私自身も以前、中途採用で某人事系コンサルティングファームを受けた際、「TG-WEB?」が出てきましたが、ほぼ無対策だったので速攻で落とされてしまいました(対策しても多分落ちたと思いますが)。
それはさておき、企業が適性検査に何をどの程度求めるかは企業によって様々です。しかし中途採用で適性検査を課してくる以上、最低限の対策はしておいた方がベターです。
本記事では、転職活動で新卒以来久しぶりに適性検査を受ける方向けに、「どの程度の事前準備が必要なのか?」「主な適性検査の種類」そして「適性検査対策・注意点」について書いていきたいと思います。
※基本的にはSPI3を題材にした記事となります。
適性検査に事前準備はどの程度必要か?
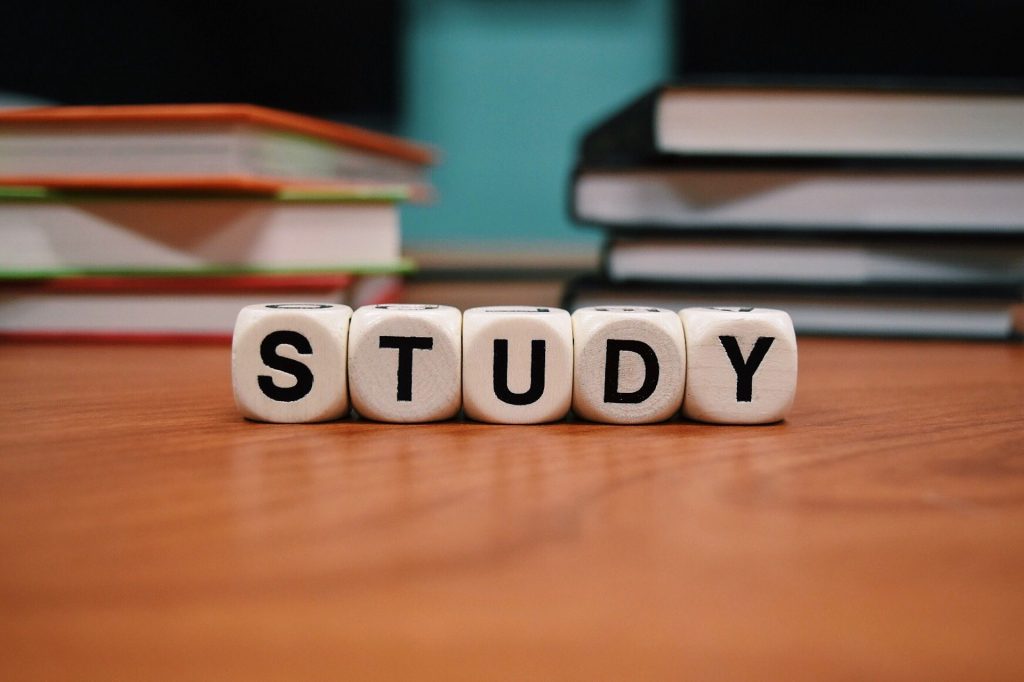
「中途採用の適性検査では何割取得を目指すべきか?」についてです。
新卒採用ではご存知のように、SPI3などのWEBテストを足切り目的で使用する大手企業も数多くあり、企業ごとに足切り基準が存在します。「6割以上」「7割以上」~といったように企業によってそれぞれ独自に基準を設けています。
著名なコンサルティングファームなど、職種によってはより高い基準を設けている職種もあり、これをクリアしないと次の面接には進めません。
同様に中途採用でも適性検査の結果を新卒並みに重視する企業、職種があります。私が以前某企業の人事部で中途採用担当をしていた時にも、
SPI2の知的能力分野(言語・非言語)での評価が※7段階中5以上でなければ不採用
という足切り基準がありました(事務職、営業職、新卒、中途問わず全て同じ基準を求められる)
このSPI2の7段階評価は少し昔の話です。現在はSPI3でレポート形式も変わっているため、これ自体あまり意味をなしませんが、「中途採用でも適性検査で足切りする場合はある」という事です。
ではこの基準をクリアするためには、 どの程度のスコアを取れば良いのか?
実際のところ、SPIの”Raw Score”は企業側のレポートにも表示されないため、企業側でも応募者の正確な点数は分かりません。あくまで実感値ですが、6~7割程度は必要と思います。(私自身が当時入社時に受けたSPIの感触と、その後実際に人事部員として自分の結果レポートを見ての単なる”推測”です。)
これはあくまで1例に過ぎず、企業・職種によってこれより高い基準もあれば低い基準もあると思いますが、
適性検査の言語・非言語については、最低限7割取れるぐらいの事前準備をしておきましょう。
特に言語・非言語能力を重視している企業・職種では、場合によっては通過しない場合もあるかもしれませんが、7割取れれば概ね期待水準を満たす企業は多いと思います。

適性検査結果をどの程度重視するかについては、応募者の年齢や経験にもよります。さすがに大学を出てから20年も経つベテランに「筆記テストの結果が悪いから」というだけで不合格にするのはナンセンスとも言えます。適性検査は参考程度に見ている企業も多々ありますので、一応付け加えておきます。
適性検査の種類について
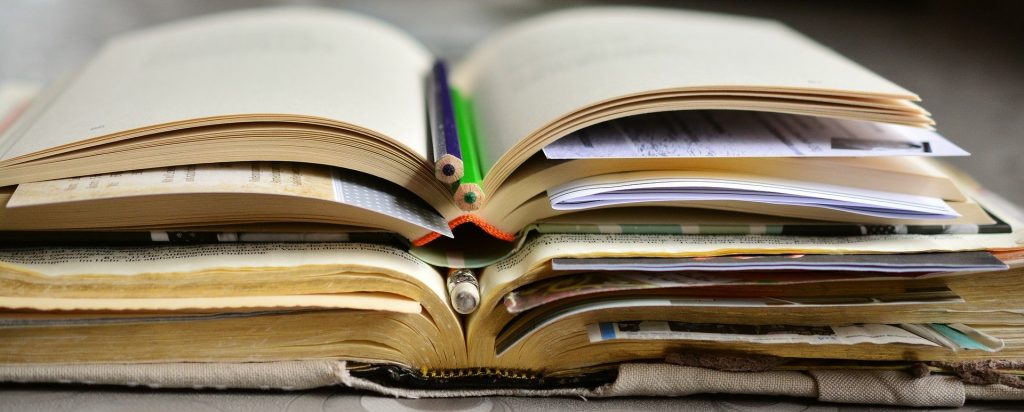
就職試験で使用されている適性検査は20種類以上(あるいはもっと)あると思いますが、主要なものを幾つか挙げておきます。
(それぞれの適性検査の特徴や全ての種類を網羅的に知りたい方は、他のまとめ記事等をご覧ください)
・SPI3(リクルート社)
・玉手箱シリーズ(日本SHL社)
・GAB/CAB (日本SHL社)
・TG-WEB(ヒューマネージ社)
・3Eテスト(エン・ジャパン社)
・内田クレペリン検査(日本・精神技術研究所)
他にレアケースですが、「自社独自の筆記試験」という場合もあります。
私が3年程前に、某著名国内大手のグループ企業で受けた適性検査は、漢字や歴史、数学など公務員試験を思いっきり下位互換したような簡単なペーパーテストでした。
(これ、ちゃんと赤ペン採点しているのか?単に「昔からやっているから」という理由で形式的にやっているだけという印象でした)
それはさておき、適性検査の種類は沢山ありますが、測定項目は概ね以下のようなものです。これに英語が加わる場合もあります。
- 「言語・非言語の知的能力」
- 「性格特性」
- 「職務適性」
- 「組織適応度」
そして「どの企業でどの適性検査が使われているのか?」については、
- 転職エージェントの担当者に情報がないか聞いてみる。
- ネットやSNSで探してみる(いつの情報なのかは注意)。
企業がわざわざ積極的に発信する情報ではないため、上記で確認しても分からなければ一番多く利用されているSPI3の対策本を1冊やっておくのが良いと思います。
次ページは適性検査対策についてです。
適性検査対策

言語・非言語検査対策
SPI3を例に話を進めますが、各問題はそれほど難しくないです。中には言語・非言語とも満点近く取る方もいます。
しかし、先述のように新卒やコンサル、外資金融など一定以上の知的水準を求められるような一部業界、職種を除けば「言語・非言語で7割を取れるぐらいに対策すれば十分」というのが本記事の主旨です。
もちろん時間が充分ある方は、満点目指してきっちりやって頂きたいですが、そうでない場合、テスト対策はほどほどにして、面接対策をしっかりやる方が内定は近いと思います。
それをふまえて、適性検査の対策本を1冊ご紹介しておきます。自分も以前このシリーズで対策しました。 昔学校で学んだ最低限の国語・算数力があれば1冊やると記憶がだいぶ蘇ると思います。
SPI3には幾つかの受検方式があります。主要なものとしては「テストセンター」「WEBテスティング」「ペーパーテスト」です。
次に、学習する上で意識した方が良いと思う事を以下に記載します。
普段電車通勤されている方は、電車内のスキマ時間に勉強すると大変効率は良いのですが、経験上、非言語の計算問題は本に目を通して頭で解き方をイメージするだけでなく、実際に紙に書いて計算までやらないと定着しないと思います。
忙しくて時間がない方は1日1問ずつ、時間にして10分~15分でも良いので、机に向かって学習してみて下さい。
そしてもう一つ、学習する上で重要なポイントは「回答スピード」です。問題演習する際は必ず時間を計って、回答目安時間内で解く意識で学習する事を強くお勧めします。
特に、「昔新卒の就職活動で紙のSPIを受けたのが最後で、その後全く転職活動をして来なかった」等、WEBテストに慣れていない方は、本命企業の受検前に一度WEBテストを体験しておいて下さい。
紙と違ってWEBは「待ってくれない」んですよね。
1問あたりの回答時間が決まっており、それがパラメーターで表示されて砂時計のようにどんどん減っていきます。パラメーターがなくなると強制的に次の問題へ遷移していきます。ペーパーテストのように「まずできるところから解いていくか」みたいには出来ません。
「え、終わり?もうちょっとで解けたのに・・」私も以前、初めてWEBテスティングを受けて焦ったのを覚えています。
SPI3に限らず、どの適性検査にも共通して言える事ですが、限られた時間の中で沢山の問題を解かなければなりません。「じっくりと考えて解く」のではなく、「テンポよく反射的に解く」事が求められます。ですので「じっくり時間をかければ解ける」というのはあまり意味がないです。
以上を意識してSPI3の対策本を1冊仕上げる。更に復習でもう1~2周まわしてからコンスタントに7割取れれば、最低限の対策としては十分じゃないかと思います(到達度に応じて復習の回数を増やしたり、苦手分野の克服など、調整してみて下さい)。
性格・職務適性検査対策
私は以前人事部で中途採用の担当をしていましたが、私がいた人事部では性格・職務適性検査の調査結果は面接の際の参考資料として重視していました。
私の会社では性格検査の結果だけで足切りする事はなかったですが、面接時に質問のきっかけにしたり、面接での受け答えの印象と差異が無いかなどを見ていました。初見の相手をより正確に知るために重視している人事担当者の方も多いと思います。
そして、検査結果のどの指標を重視しているかは企業や職種によって異なります。
わかりやすい例でいえば、ベンチャー企業の営業職などでは、検査結果から出てくる「自立心」「達成意欲」などの指標が重視されますが、安定企業などでは「協調性」「規律性」などが重視される傾向です。また、「事務職」では「正確性」も重視されるでしょう。
このように適性検査に対する企業側の期待値や思惑は色々ありますが、受検する側として心掛けておくべきことは、自分を無理に良く見せようと意識して回答をするのではなく、自分の感じたままに正直に回答する事に尽きると思います。
学歴や能力が高くても価値観や職務適性が合わなければ、期待通りに活躍できないばかりか、最悪早期離職に繋がってしまう事を企業や人事部も理解しています。
応募者としても自分に合わない会社に無理に内定を得る事が目的ではなく、自分に合った会社で長く活躍する事が目的のはずだと思いますので。
また、性格検査には「ライスケール(ウソ発見器)」の問題が仕込まれている場合もあります。
例えば、
「私は人生で一度も嘘をついたことがない」→「はい」(「そんなことはありえない→嘘つき」とみなされる)など。
人事部が受け取る検査結果レポートには「回答の信頼性」という項目もあって、嘘をついた回答は分かってしまう場合もありますし、印象が悪くなります。こうした点からも正直に回答することをおススメします。
本記事は以上です。最後まで読んで頂きありがとうございました。