やりたいことはなくても良い!?

筆者が就職活動をしたのは1999年(平成11年)ですので、ちょうど就職氷河期ど真ん中の頃でした。その後企業の人事部で新卒・中途採用担当をしたほか、何度かの転職を経て、現在は人事労務関連の仕事についています。
私自身の新卒の時の就活はそれほど良い思い出はありません。
周りに流されて就職活動を始めたものの、「この会社本当に自分が行きたいところなのか?」「逆にどういう会社なら良いのか?」といった選社軸がまるで定まらず、前半は何十社もお祈り。同時に周囲の仲間の就職意識の高さに驚きました。
就職難も手伝って他の人より随分時間がかかりましたが、最終的には何社か内定をもらいました。自分で主体的に選んだというよりは、単に受かったところに行っただけですが、今振り返るとそれはそれで良かったと思っています。
その後転職も経ましたが、企業の人事部など色々経験して今社会人20年を超えました。改めて当時の自分の就活を振り返ってみると、伝えられる事があるのではないかと思った次第です。
それは「やりたいことがない」についてです。当時私もそうでした。新卒の就活当初はこんなふうに考えてました。

- 毎回やりたいことは何ですか?と聞かれてもわからない。多分やりたいことは(現段階では)ない。
- 数撃てばどこかには受かるんじゃないかな。。
全くナメてました。。企業にも失礼ですよね。。。
でも大丈夫です。世の中そんなに就職意識が高い人ばかりではありませんし、社会に出ている諸先輩方にもいろんな方がいます。内心どう思ってても別に良いのです。ぶっちゃけた話、本当にやりたい事なんて見えてない人の方が多いと思っています。
そこで本記事で言いたい事ですが、
- 現段階で本当にやりたいことは見つかっていないという事は肯定する。
- そのうえで、(後で変わるかもしれないが)とりあえず現時点での自分のやりたいことを準備する努力はしてみよう。
社会人の先輩として一つだけ偉そうに言わせて頂くならば、やりたいことなんて今後いくらでも出てくるかもしれないし、今やりたいと思っている事でも今後きっと変わります。
結局新卒の面接に受かるかどうかは、
「とりあえずでも現時点での自分のやりたいこと」を(他人も納得できる構成で)準備できているか?」です。一言で言えば、「自己分析」をきちんとやる事です。現状の仮説で良いのです。
そして自己分析の結果出て来た仮説が「本当かな?」と自分の中でモヤモヤしても、一旦決めた以上そこは割り切って堂々と演じましょう。
本当にやりたい事が明確な方も一定数いますので、それはそれで良しとして、そうでない多くの方はこの就活のタイミングで自己分析をきちんと行って、現段階での自分の答えを見出す努力をした人が面接に受かる。
「このちょっとした努力の差が明暗を分けているだけ」というのが私個人の総括です。
さて、本記事ですが「やりたいことがない人が自己分析を行うためのきっかけ」として以下の2つをご紹介します。
- 「職種」ではなく「仕事の性質」で考える
- 「アルバイトの経験」から掘り下げる
なお、前提の確認ですが現段階でやりたいことがない方は、
- やりたい事が見つかるまで就職しない
- とりあえずどこかに就職する
の二択だと思いますが、本記事はこのうち「2.やりたいことは見つかっていないが、とりあえずどこかに就職する」場合を想定して書いております。
派手なアピールは必要ない

本題に入る前に、私自身が以前人事部で新卒採用の面接官を担当していた経験から感じていたことを先に2点お伝えしたいと思います。どちらも本題に関係します。
1点目は「面接での派手なアピールは有効なのか?」という点です。新卒採用の面接をしていて、学生からの自己アピールでよく出てくる話として、
- 体育会でキャプテンをしていました!
- 海外留学の経験があります!
といった”派手な”経験のアピールがあります。こうした経験がある事自体が高評価につながるのか?逆にこうした経験をしていないと評価されないのか?どちらも答えは「Noです」。
こうした体験”自体”が高評価につながるのではなく、それだけではただの「材料です」。
- そこから学んだ事は何か?
- それを今後どう活かしていきたいのか?
といったストーリーで伝えられなければ「で?」となってしまいますし、材料の大小は本質ではありません。「アピールできる立派な経験がないから自分はダメなんだ」と思う必要は全くありません。
”大学での勉強を通じての興味関心”や”アルバイトでの経験”、”友人との関わりの中での自分の役割”など、日常のちょっとした体験の中から、ご自身が学んだことや今後活かせそうな内容を探しましょう。
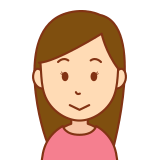
そういえば、いつも友達3人で行動しているけど、私はマイペースな2人の間に入って、うまく調整したり中を取り持ったりするコーディネートみたいな役割かも。そういう役回りは嫌いじゃないな。

調整役とかコーディネーター系の職種にも適性がありそうですね。
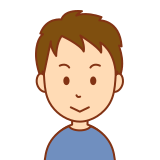
前に単発のアルバイトをしていた時、袋詰めの単純作業だったけど頭を使う必要がなくて全然苦にならなかったな。一緒にやった友人はすぐに飽きてたけど。

それなら事務系職種なんかも結構合ってるんじゃないですか?
どうでしょう?派手な経験がなくとも自分にもできそうだと思えて来ませんか?
次ページ「やりたい事がない人向け ~自己分析の切り口~」へ続く