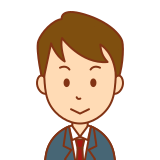
社労士試験に合格して転職したい!
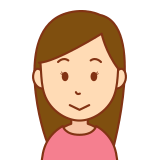
資格予備校に通う時間はないので、独学で何とかならないかな?

社労士試験、合格したいですよね!
筆者は平成25年の社労士試験に合格しましたが、1度目は落ちて2度目でようやく受かりました。私の場合、厳密にいうと独学ではありません。都内の大手資格予備校の「DVD通信講座」を主に週末に自宅で受講しました。
ですので、書店などでテキストを買いそろえるよりは多少費用はかかっていますが、学習計画は全て自分で立てて、自宅で学習を進めました。
本題に話を戻します。社労士試験の合格に必要な学習時間は1,000時間程度とも言われています。経験上、働きながら社労士合格を目指す方は、以下をクリアしていく必要があると思っています。
- いかにして学習時間を捻出するか?
- 限られた学習時間を以下に効率的に使って行くか?(今回の主なテーマ)
- いかにしてモチベーションを維持するか?
実際のところ結構大変ですよね。筆者も1度目の受験の際は、だいぶサボってしまい、準備不足で不合格でした。そこからまた1年、長いですよね。。
今回は、上記のうち「2.限られた学習時間をいかに効率的に使って行くか?」、つまり私自身が実践して合格につながった「効率的な学習のポイント」を全4回に分けてお伝えします。
現在独学中の方、そして予備校のテキストで学習している方も、効率的に独習する際の参考になれば幸いです。
科目特性毎に試験科目をグルーピング
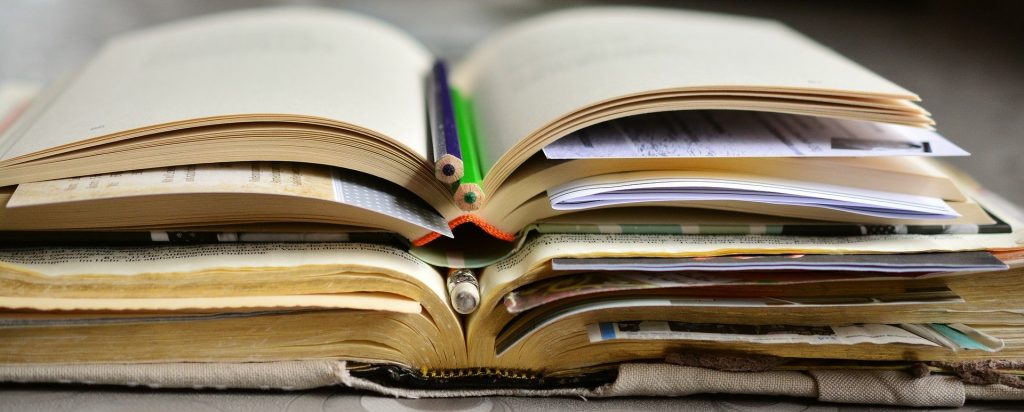
社労士試験は暗記試験です。科目数も多く、試験期間を通してまさに忘却との戦いでした。「あちらを覚えたらこちらが抜けている」といった事を本試験開始の瞬間まで延々と繰り返します。合格者でもこんな感じです。
結局は、「隅から根性でゴリゴリ暗記していくだけ」なのですが、科目の特性によって「まとめて学習した方が暗記効率が良いもの」「先に覚えてもすぐ忘れるので、後回しにした方が良いもの」が存在します。本記事ではまず、「試験科目のグルーピング」についてお伝えします。
社労士試験の試験科目は以下の10科目です。私はまず学習に先立って、これらの10科目を以下5つにグルーピングしました。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 雇用保険法
- 労災保険法
- 徴収法
- 労一
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金法
- 社一
雇用保険・労災保険・徴収法
国年・厚年
安全衛生・労一・社一
労基
健保
※グループ名称は自称です
グルーピングの趣旨
上記のグルーピングを行った趣旨は以下の通りです。
- 雇用保険と労災保険はそれぞれ異なる法律ですが、似た様な仕組みや用語が多いので、双方の相違点を意識しながら学習していくのが効率的です。
- 択一でのそれぞれの配点は「雇用保険:7点」「労災保険:7点」「徴収法:6点」の計20点。このうち徴収法は、雇用保険、労災保険の問題中に各3問ずつ出題されます。
- 雇用保険、労災保険ではしばしば難問も出題されるため、合格に向けては徴収法の学習は欠かせません(用語等がとっつきづらいですが、決して難しくはないので捨てるのはNGです)。
- 年金制度の仕組みを理解するのに時間がかかる科目です。しかし、年金科目への苦手意識さえなくなれば、国年・厚年併せて択一問題の20/70点を占めるだけに、安定したポイントゲッターとして計算できます。試験学習前半期に時間をかけてでも克服しておくべき科目です。
- 国民年金、厚生年金双方の共通点・相違点を意識しながら学習するのが効率的です。
- 労働安全衛生法は、安全衛生管理体制や特定機械など、ややこしい名称や数字が沢山出てきて、非常に覚えづらく忘れやすいです。暗記科目中の暗記科目です。直前期に回しましょう。
- 労一、社一の一般常識系は出題範囲が非常に広く、ある意味一番対策しづらいです。学習したところが出題されるとは限らず、選択式試験では足元をすくわれる可能性も高いです。後述しますが、直前期に効率的に要点を押さえるのがベターです。
上記、「労働保険グループ」と「年金グループ」の習得には時間がかかると思いますが、学習初期段階でこれらの基礎固めをしてしまえば、択一試験のうち40/70点はカバーしたことになります。気持ちの面でも余裕ができます。
そして直前期に暗記科目を中心に上積みをすることで、択一では最終的に50/70点以上の取得を目指しましょう。以下、参考までにご覧ください(厚労省:社会保険労務士試験の結果について)
参考 過去5年間の社労士試験の択一合格基準
| 西暦 | 和暦 | 回次 | 合格基準(択一) | 救済(択一) | 合格率 |
| 2020 | 令和2年 | 52 | 44/70 | 6.4% | |
| 2019 | 令和元年 | 51 | 43/70 | 6.6% | |
| 2018 | 平成30年 | 50 | 45/70 | 6.3% | |
| 2017 | 平成29年 | 49 | 45/70 | 厚年:3点以上 | 6.8% |
| 2016 | 平成28年 | 48 | 42/70 | 一般常識(労一、社一)・厚年・国年:3点以上 | 4.4% |
学習順に話を戻します。要は、一番最初に安全衛生法を学習しても直前期にはほぼ全て抜けているでしょうし、直前期に年金系をやろうとしても思った以上に時間がかかり、焦るばかりで時間切れになってしまうため、学習の順番は学習効率の面でも大切です。
ちなみに私は以下の順番で学習しました。
- 年金グループ(国年、厚年)
- 労働保険グループ(雇用保険・労災保険・徴収法)
- 労基
- 健保
- 直前暗記グループ(安全衛生・労一・社一)
※「労働基準法」「健康保険」の順番は(暗記科目より前ならば)別にどこでも良いと思います。どちらも出題に難問が混じる場合も多く、満点取得は中々難しい印象です。一つの科目の重箱の隅をつつくよりもまずは、できれば年内ぐらいで1~4を網羅的に押さえていく事を意識しましょう。
本記事は以上です。次記事「合格者が語る「社労士試験」”半”独学!?勉強法 vol.2」では、この学習順に沿って「どうやって学習していくのか?」「いつまでにどの程度終えるべきなのか?」についてお伝えします↓


